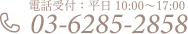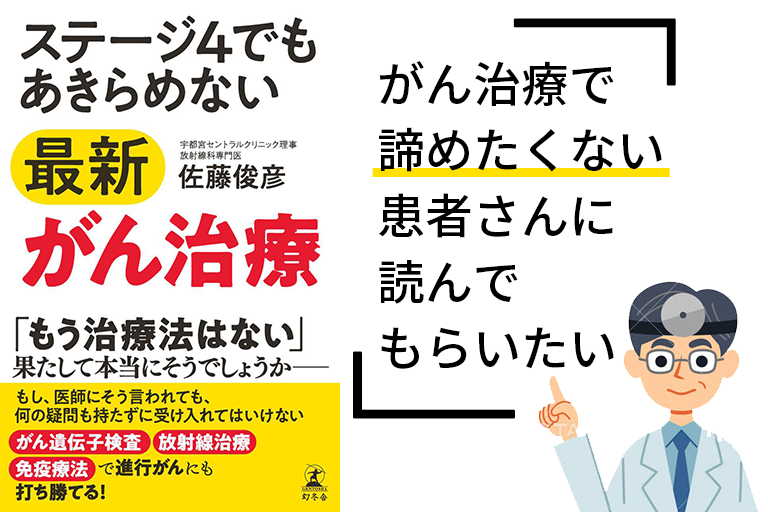16,659
16,659
抗がん剤治療が中止になる基準や理由とは?中止した場合の余命や選択肢も解説

がん治療において、何らかの理由で抗がん剤治療を継続するのが難しくなるケースがあります。抗がん剤を中止する状況に直面した際に、今後の見通しや治療方針について大きな不安を感じることもあるでしょう。
今回は、抗がん剤治療を中止する具体的な基準や理由、中止後の余命に関する正しい知識を詳しく解説します。さらに、抗がん剤治療を中止した後も実施できる可能性がある治療の選択肢についても確認していきましょう。
目次
抗がん剤治療が中止になる基準や理由

抗がん剤治療が中止になる基準や理由について、4つのポイントに分けて解説しましょう。
治療効果が得られなくなったとき
抗がん剤は、使用しても効果が得られない「薬剤耐性」の状態であると、治療中止となります。
薬剤耐性には、初めから抗がん剤が効かないケースと、徐々に効果が得られなくなるケースに分けられます。がんが薬剤耐性となる主なメカニズムについて、以下より解説しましょう。
抗がん剤の取り込みや排出を変化させる
抗がん剤のなかには、がん細胞内に取り込まれて効果を発揮するものがあります。
がん細胞は、細胞内に薬剤を運ぶトランスポーターの性質を変えたり、数を減らしたりすることで、抗がん剤が取り込まれないようにするのです。ほかにもがん細胞は、細胞膜内から外へ物質を排出させるトランスポーターの数を増やして、抗がん剤を排出しやすくします。
これらのがん細胞の変化により、抗がん剤の効果が弱まるのです。
抗がん剤の活性化を妨げる
抗がん剤には、体内で酵素の働きを受けてから、がんを攻撃できる状態になるものがあります。白血病の治療に使われるシタラビンは、そのまま投与しただけでは効果がなく、体内酵素によって活性化された後に効果を発揮します。
しかし、がん細胞は、薬剤を活性化させる酵素の働きを弱めたり、変化させたりすることで、薬の効果を弱める働きをします。体内には、有害物質や薬剤を分解するグルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)という解毒酵素があります。がん細胞はGSTの量を増やして抗がん剤を不活化し、効果を弱めるのです。
抗がん剤の標的タンパク質を変化させる
抗がん剤のなかには、特定の分子やタンパク質に対して作用するものがありますが、時間の経過とともにがん細胞が変化することで、抗がん剤からの攻撃を回避することがあります。
アントラサイクリン系抗がん剤のドキソルビシンは、がん細胞のトポイソメラーゼという酵素に作用して増殖を抑えます。治療を進めていくうちに、がん細胞のトポイソメラーゼに変異が起きると、ドキソルビシンの効果が減弱するのです。
副作用が重症である場合
抗がん剤治療が中止になる理由に、副作用が影響することがあります。以下のように副作用が重症化すると、治療継続が困難になるケースが多いです。
| 骨髄抑制 | 白血球や血小板の減少により、感染症や出血のリスクが高まる |
| 神経障害 | 手足のしびれが強くなり、日常生活に支障をきたす |
| 消化器症状 | 強い吐き気や下痢などが続くことで、栄養状態が悪化する |
| 臓器障害 | 肝機能障害や腎機能障害が生じると、抗がん剤の代謝や排泄が遅れて、全身状態が悪化する可能性がある |
全身状態が悪化した場合
患者さんの全身状態が悪化した場合も、抗がん剤治療を中止することが多いです。患者さんの全身状態を評価する基準に、パフォーマンス・ステータス(PS)が用いられます。PSは、0から4の5段階に分けられ、それぞれの目安は以下のとおりです。
| PS 0 | 体調は非常に良好。病気になる前と変わらず、日常生活や仕事などのすべての活動を問題なく行える状態。 |
| PS 1 | 体に負担のかかる激しい活動を避ける必要はあるが、歩くことはでき、日常的な軽い活動や座ってできる仕事なら問題なく行える状態。 |
| PS 2 | 自分で歩くことができ、身の回りのこと(食事・入浴・着替えなど)は自力でできるが、仕事や作業はできない状態。起きている時間の半分以上は、ベッドから起き上がって生活している。 |
| PS 3 | 身の回りのことは限られたことしかできず、起きている時間の半分以上をベッドや椅子で過ごしている状態。 |
| PS 4 | 体の機能が失われた状態で、身の回りのことが自力でできない。常にベッドや椅子で生活している。 |
PSが3以上の場合は、積極的な抗がん剤治療をおこなわないことが一般的です。
患者が抗がん剤治療を希望しないとき
抗がん剤治療を中止する理由の1つに、患者さんの希望もあります。患者さんが抗がん剤治療を希望しない背景には、以下のものが挙げられます。
- 副作用による生活の質の低下
- 経済的な負担
- 患者さんの人生観や価値観
抗がん剤治療を中止したときの余命

抗がん剤を中止したときの余命について状況ごとに解説します。宣告された余命と実際の生存期間に違いが出る背景についても確認しましょう。
がんの種類やステージによる違い
がんの種類やステージによって、抗がん剤治療を中止した後の余命は大きく異なります。
ステージ4の固形がんの場合、全体の5年生存率は約16%ですが、前立腺がんは約43%であるのに対し、食道・胃・肝臓・肺などは10%以下です。
膵臓がんでは、術後補助化学療法(抗がん剤治療)をおこなわない場合、生存期間の中央値は20.2ヶ月と学術論文で報告されました。別の学術論文では、膵臓がん手術後に抗がん剤のS-1で補助化学療法をおこなった場合の生存期間中央値は、46.5ヶ月と報告されています。
いくつかの抗がん剤治療をおこなっている転移性大腸がんにおいて、抗がん剤治療をおこなわない場合の生存期間中央値は6.6ヶ月、おこなった場合は9.0ヶ月と報告された学術論文があります。
治療中止した理由による違い
抗がん剤治療を中止した理由によっても余命の予測は異なります。
薬剤耐性が生じて抗がん剤の効果がなくなった場合、他に有効なものがない場合は、がんの進行速度や全身状態に応じて余命が左右されます。
抗がん剤の副作用で治療中止した場合は、症状が回復して他の治療が実施できれば、生活の質が改善し、結果として余命が延びる可能性があるでしょう。
患者さんの希望で中止した場合、早期に抗がん剤治療を中止すると、がんの進行により余命は短くなる可能性が高くなりますが、がんの種類や患者さんの体力などにより、余命の個人差は大きくなります。
宣告された余命と実際の生存期間の違い
余命を患者さんに伝える場合、医師が用いるのは主に「生存期間中央値」というデータで、同じがん種・同じステージの患者を対象にした統計データのことです。患者さんの集団の50%が生存する期間を指しているため、個々の患者さんに必ずしも当てはまるものではありません。
宣告された余命と実際の生存期間に差が生じる主な理由は以下のとおりです。
| 個人差 | 同じがん種でも、患者さんごとに年齢・体力・合併症などが異なる。全身状態が悪いケースでは、余命が予測より短くなることもある。 |
| 抗がん剤の治療効果の違い | 同じ抗がん剤治療をおこなってきた場合でも、それまでの効果の現れ方に個人差があるため余命が異なる。 |
| 抗がん剤以外の治療法 | 余命宣告後におこなう治療によっては、生活の質が改善し、生存期間が延びる可能性がある |
余命の宣告については以下の記事でも解説していますので、ぜひお読みください。
>>余命宣告されてもがんは治る?余命の判断基準や宣告のタイミングなど解説
抗がん剤治療を中止した後におこなう治療の選択肢

抗がん剤治療を中止した後でも、実施できる見込みのある治療について解説しましょう。
緩和ケア
緩和ケアは、がんによる身体的・精神的なつらさをやわらげる治療です。日本では「緩和ケア=終末期」というイメージで捉えられていることが多くみられますが、実際はがんの進行度にかかわらず実施されています。
緩和ケアでおこなわれる主な治療内容は以下のとおりです。
- 痛みのコントロール
- 吐き気の症状改善
- 抑うつや不安症状の軽減
- 食生活や栄養のサポート
- 生活環境の整備
がん治療を始めて、早期のうちから緩和ケアに取り組むと、生存期間が延長すると学術論文で報告されています。
手術
がんの種類・患者さんの全身状態や病状によっては、手術がおこなわれることがあります。手術可能とされる主な条件は以下のとおりです。
- 転移したがんが限定的で切除できる
- 原発巣が周りの重要な臓器に達しておらず切除できる
- 患者さんの全身状態が良好で手術に耐えられる
がん組織を切除する手術のみならず、がんによって食道や腸が詰まってしまいそうになった場合も、症状をやわらげるために手術が実施されることがあります。
放射線治療
放射線治療は、抗がん剤治療を中止した後でも受けられる治療の1つです。がん組織によって引き起こされる以下の症状をやわらげるためにおこないます。
- がんの増殖や骨転移に伴う痛み
- 出血
- 気道や消化管の詰まり
- 神経圧迫による麻痺やしびれ
1回の治療時間は10分~15分程度、治療日数は1日~10日程度で終わるため、通院で対応可能です。
免疫細胞療法
免疫細胞療法は、自分の血液から免疫細胞を採取し、培養・活性化させてから再び体内に戻す方法であり、自由診療でおこなわれています。主な免疫細胞療法の種類は以下のとおりです。
| 免疫BAK療法 | ・γδT細胞とNK細胞を使用 ・血液から免疫細胞を採取し、培養してから、活性化処理をした後に再び体内に戻す |
| 樹状細胞療法 | ・樹状細胞を利用 ・血液から取り出した単球を樹状細胞に育てた後、がん抗原(がんの特徴)を覚えさせてから、再び体内に戻す |
| NK細胞療法 | ・NK細胞を利用 ・血液からNK細胞を取り出し、特殊な環境で培養してから、再び体内に戻す |
免疫細胞療法は、いずれも自由診療であるため、治療にかかる費用は全額自己負担となります。
代替療法
抗がん剤治療を中止した後は、代替療法を取り入れるケースもあります。主な代替療法には、サプリメント・健康食品・鍼灸・温熱療法・マインドフルネスなどが挙げられます。
代替療法は、がんの進行を抑える・がんを小さくするといった科学的根拠はないため、取り入れる際は注意が必要です。がんによる不快な症状をやわらげたり、精神的な辛さを軽くしたりするなど、生活の質を保つ目的での利用にとどめましょう。
治療法がないと言われた場合は、以下の記事でも解説していますのであわせてお読みください。
>>がんの治療法がないと言われたら?次に取るべき”3ステップ”とは
抗がん剤治療を中止する際に注意すること

抗がん剤治療を中止する際は、慎重な判断が必要です。注意することや検討した方が良い点について解説しましょう。
今後の見通しについて確認する
抗がん剤治療を中止することを提案されたら、主治医に以下の内容を確認しましょう。
- 抗がん剤治療を中止する理由
- 現在の病状
- 治療中止後に予想される経過
- 今後の治療方針
- 日常生活で注意すること
現在の病状と今後起こりうる症状を理解しておくと、精神的な準備ができて、漠然とした不安を取り除くことができます。今後の治療方針を確認すると、必要な医療サービスの手配などをあらかじめ準備することが可能です。
セカンドオピニオンを検討する
抗がん剤治療の中止は、治療方針の変更を意味し、慎重な判断をするため、セカンドオピニオンを検討すると良いでしょう。セカンドオピニオンを受けるメリットは大きく2つあります。
1つは、より適切な判断につながる可能性があることです。抗がん剤治療を中止する目安はいくつかありますが、統一した基準があるわけではありません。主治医とは別の医師から意見を聞くことで、治療中止になった理由に対する理解が深まることがあります。
もう1つは、今後の治療について、選択肢が増える可能性があることです。セカンドオピニオンの医師は、主治医と異なる目線で現在の状況を評価するため、抗がん剤治療を継続できる可能性や、主治医から示された治療方針と異なる治療を提案される可能性があります。
抗がん剤中止後のケアプランを考える
抗がん剤の使用を中止することは、治療そのものを中止するという意味ではありません。抗がん剤中止後の治療について、以下のように希望することを考えておきましょう。
- 緩和ケアや自由診療など受けたい治療方法
- 自宅での療養、または施設での療養
- 必要な医療・介護サービスの手配
抗がん剤治療を中止した場合の余命などに関するよくある質問

抗がん剤治療を中止した場合の余命や症状などについて、よくある質問をQ&A方式で解説しましょう。
抗がん剤を中止すると必ず余命が短くなりますか?
抗がん剤治療を中止した場合、必ず余命が短くなるわけではありません。抗がん剤はあらゆるがんに対して100%の効果があるわけではなく、抗がん剤治療を単独でおこなった場合、効果があるのは30%~40%とされています。
また、がんの種類や患者の全身状態によっても、余命は個人差が大きくなります。そのため「抗がん剤が効かない=余命が短い」と簡単に考えられるものではないのです。
抗がん剤を中止するとどのような体調変化が起きますか?
抗がん剤の副作用による症状は、個人差が大きく、使用していた薬剤や治療期間によっても異なります。時間の経過とともに軽快する可能性のある副作用症状は、吐き気・嘔吐・脱毛・倦怠感・食欲不振です。抗がん剤中止後も長期間続く可能性のあるものは、神経障害や心毒性があります。
がん自体の症状は、がんが進行しているほど変化が早く、ステージ4の場合は月単位で大きな変化があります。がんの進行に伴う症状は、痛み・出血・体重減少・リンパ節の腫れなどです。転移がんがあれば、転移した臓器によってさまざまな症状が現われます。肝転移であれば黄疸や腹水、骨転移であれば病的骨折や骨の痛みなどがあります。
抗がん剤治療を中止したときに主治医から告げられる余命予測はどの程度正確ですか?
医師から告げられる余命予測は、必ずしも正確ではありません。国立がん研究センター中央病院がおこなった研究調査では、進行がん患者75人の生存期間の予測において、医師の余命宣告どおりだったケースは約3割にとどまっています。
余命の予測には、ある集団において半数の患者さんが亡くなるまでの期間を示す、生存期間中央値(median survival time:MST)が用いられており、医師はこの値を参考にしているケースが多いです。実際の生存期間は、がんの進行状況や性質、患者さんの全身状態などの影響を受けるため、余命予測は1つの目安として考えるようにしましょう。
まとめ

抗がん剤治療が中止となる背景には、効果の減弱・重篤な副作用・全身状態の悪化・患者さんの希望が挙げられます。
中止後の余命は、がんの種類や進行度、中止する理由などによって個人差があり、医師から告げられる余命予測も必ずしも正確ではありません。抗がん剤を中止した後も、緩和ケア・手術・放射線治療をはじめ、治療の選択肢がいくつかあります。
抗がん剤治療の中止には慎重な判断が必要となるため、主治医と十分話し合い、今後の見通しや治療方針を確認すると良いです。必要に応じてセカンドオピニオンをおこない、患者さん本人にとって適切な治療やケアを受けるようにしましょう。