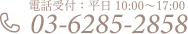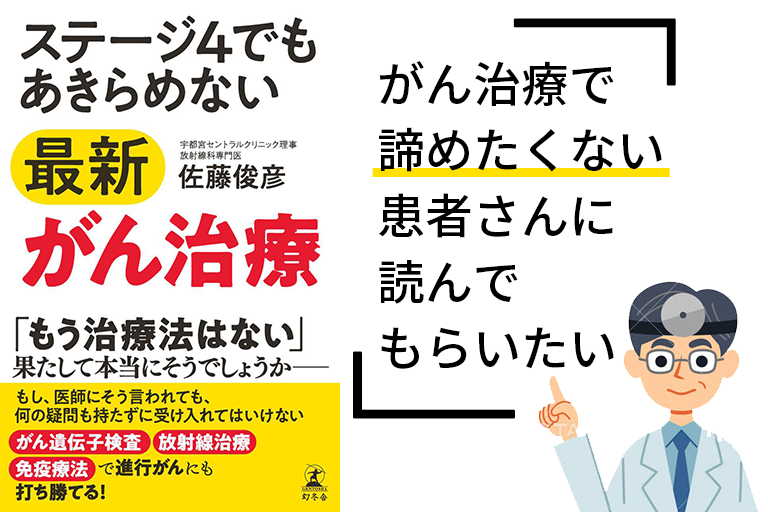348
348
がんが再発したらどうする?確認すべきことや治療方法の決め方など解説
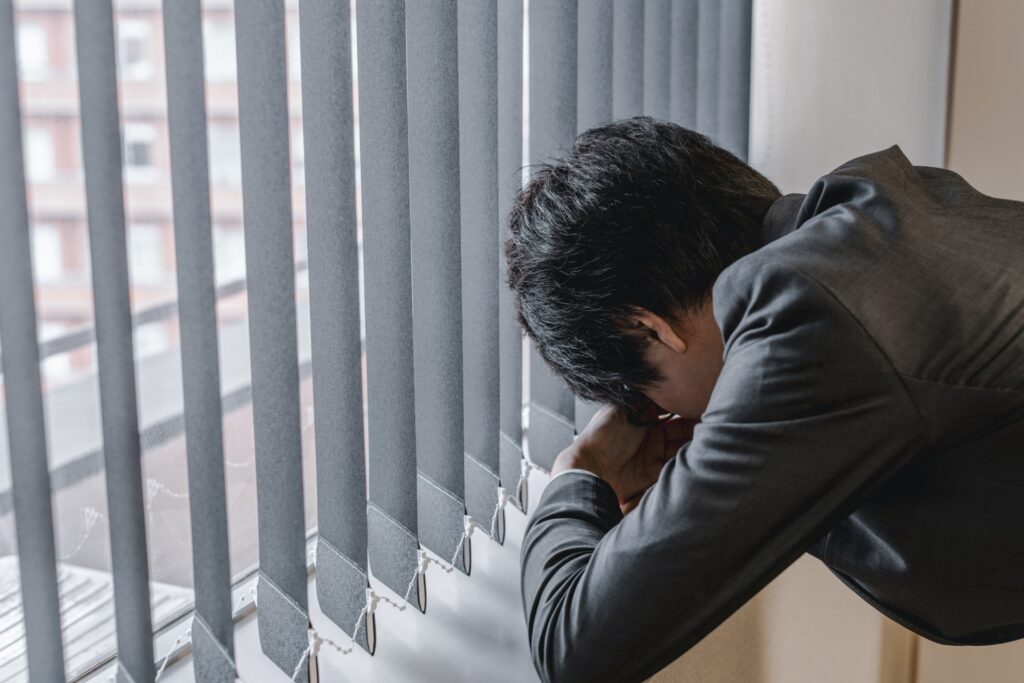
がんの再発が判明したとき、多くの方は強いショックに襲われるでしょう。有効な治療はあるのか、一体どうすれば良いのか、さまざまな不安が押し寄せて混乱してしまう方も少なくありません。
しかし、最適な選択をするためには、情報をひとつひとつ整理して冷静に判断することが大切です。
この記事では、がんが再発したら確認すべきポイントや治療方法の選択肢、さらに再発リスクを下げるための生活習慣まで詳しく解説します。正しい知識を身につけて、前向きに治療へ取り組んでいきましょう。
がんの再発とは
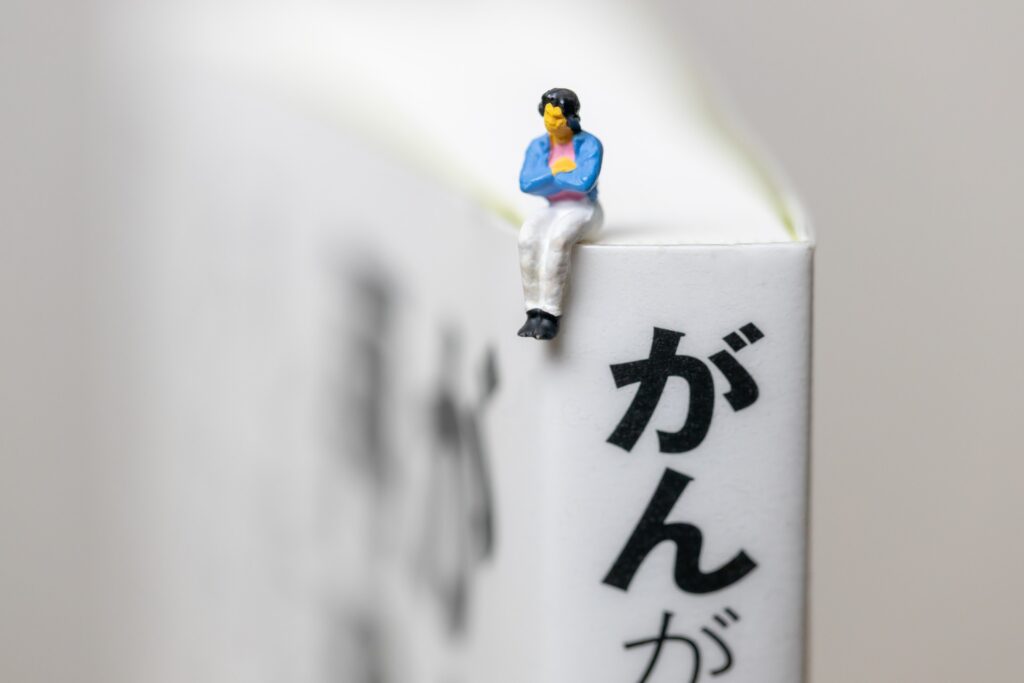
がんの再発について、メカニズムや種類について解説します。がんの再発と転移の違いについても確認しましょう。
がんの再発が起こるメカニズム
がんの再発は、治療後も目に見えない小さながん細胞が体内に残っていることで起こります。
手術や放射線治療で完全に排除しきれなかった微小ながん細胞が、時間の経過とともに再び成長したり、薬物療法で小さくなったがん組織が、治療に抵抗力を持った状態で生き残って再び増え始めたりするのです。最初にがんが生じた場所から血液やリンパ液を通じてほかの臓器へ移動し、そこで増え始めるケースもあります。
がん再発の3つの種類
がんの再発は、局所再発・領域再発・遠隔再発の3種類に分けられます。それぞれの特徴について解説しましょう。
局所再発
局所再発は、 最初に生じたがんと同じ場所、もしくはそのすぐ近くに再びがんが生じる状態を指します。主に、手術で完全に切除しきれなかったごく小さながん細胞が増え始めることが原因とされています。
局所再発は、初回治療をおこなってから、わりと早い時期に発見されることが多いです。再発しても、根治(完治)を目指せる可能性が比較的高く、再手術・放射線治療・化学療法などを組み合わせた治療がおこなわれます。
領域再発
領域再発は、最初にがんが生じた場所の近くのリンパ節や、隣接する組織にがんが生じる状態です。最初にできたがん組織からリンパ液の流れによって、周辺のリンパ節や組織にがん細胞が広がって増え始めることが原因とされています。
領域再発は、限られた範囲での再発であるため、早期に治療を始めることで、がんが体中にまん延するのを防げる場合が多いです。また、条件によっては局所再発と同様に、根治を目指した治療をおこなえるケースがあります。
遠隔再発
遠隔転移は、最初にがんが生じた場所から離れた臓器やリンパ節にがんが生じる状態です。最初に生じた場所からがん細胞が血液やリンパの流れに乗って、遠く離れた臓器やリンパ節に移動して、そこで増え始めることが原因とされています。1つの臓器だけではなく、複数の場所で同時に再発することもあり、治療が困難となるケースが多いです。
根治を目指すのは難しく、がんの進行を抑えたり症状をやわらげたりすることを目的とした全身化学療法が治療の中心となります。
がんの再発と転移の違い
がんの「再発」は、治療によってがんが一旦消失した後に再びがんが増え始めることを指します。一方「転移」は、がんが最初に生じた場所から血液やリンパ液の流れに乗って、遠く離れた臓器やリンパ節に移動し、そこで増え始めることです。医学的に「転移」は、3種類の再発のうち遠隔再発の範疇に含まれているのです。
がんが再発したら確認すること

がんが再発したと診断を受けた際に確認することを3つのポイントに分けて解説します。
再発後のステージ判定
がんが再発したら、自分の状態を正確に把握することが大切です。
再発後のステージ判定では、CT検査・MRI検査・PET-CT検査などの画像診断をおこない、局所・領域・遠隔のどの種類の再発であるかを確認します。遠隔再発である場合は、再発した場所とがんの数や大きさも確認します。
さらに最初に生じたがんから、がんの性質に変化がないかの確認も必要です。必要に応じて、がん遺伝子検査をおこないます。
再発したがんの治療目標
がんが再発した場合、がんの広がり具合によって治療目標が異なります。治療目標は大きく分けると「がんを根治させる」「がんの進行を抑える」「がんによる症状をやわらげる」の3つです。
根治を目指すことは難しいと判断された場合は、がんの進行を抑えたり、がんによる症状を緩和させたりする治療が中心となります。局所再発など条件によっては、根治を目指した治療をする可能性があります。
選択できる治療方法
再発したがんの治療には、薬物療法・放射線治療・手術の三大治療と緩和ケアがあります。薬物療法は全身に作用し、放射線治療や手術は特定の部分に治療効果があります。どの治療方法を選択するかは、がんの広がり具合・患者の全身状態・年齢などで決定するのです。緩和ケアについては、ステージにかかわらず実施されます。
がんが再発したときの治療方法の決め方と種類

がんが再発したときの治療方法の決め方や、実施できる可能性のある治療の種類について解説しましょう。
再発がんの治療方法の決め方
再発したがんの治療方法は、以下の3点を考慮して決めます。
- がんの特徴(再発部位・広がり具合・悪性度など)
- 患者さんの年齢や全身状態
- これまでの治療歴
局所再発の場合は、手術や放射線治療などを組み合わせて、根治を目指した治療がおこなわれることがあります。遠隔再発では根治を目的とした治療が難しく、ごく小さながんが体中に広がっている可能性があるため、薬物療法が中心となるケースが多くみられます。
再発がんでおこなう可能性のある治療方法
再発がんで実施される見込みのある治療は、薬物療法・放射線治療・手術などがあります。それぞれの特徴について解説しましょう。
薬物療法
薬物療法は、主に遠隔再発したがんにおいて選択されます。遠隔再発では、体中にがん細胞がまん延している可能性が高く、がんの進行を抑えて延命したり、がんによるつらい症状をやわらげたりすることが治療の目的です。
がん細胞の特性により、細胞障害性抗がん剤・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせて使用します。
放射線治療
放射線治療は、局所再発のがんを消滅させたり、遠隔再発したがんによる出血や痛みなどの症状をやわらげたりする目的でおこないます。手術のように体を切除することはないため、年齢や合併症のために手術がおこなえない場合にも適用されます。
ただし、過去に放射線治療をおこなった場合は、再発した部位によっては実施できない可能性もあるため注意が必要です。
手術
手術は、再発の条件によっておこなう目的が異なります。
局所再発では、がん組織が完全に切除できると判断される場合に根治を目指して実施されます。切除が難しいと判断された場合は、先に薬物療法や放射線治療をおこない、切除できる状態になってから手術をおこなうこともあるのです。遠隔再発では、がんによる不快な症状を緩和して生活の質を向上させるために、手術がおこなわれることがあります。
緩和ケア
緩和ケアは、がんによるつらい症状や治療にともなう副作用・合併症を軽減するためにおこないます。症状ごとの治療の種類は以下のとおりです。
| 疼痛管理 | オピオイド系鎮痛剤・神経ブロック |
| 吐き気 | 制吐剤 |
| 食欲不振 | 栄養管理・食事療法 |
| 下痢・便秘 | 症状に合わせた薬物治療 |
| メンタルケア | カウンセリング |
そのほかの治療
保険適用でおこなう治療のほかに、自由診療で受ける治療もあります。
| 陽子線治療・重粒子線治療 | 粒子線を使用した放射線治療。特定の深さで放射線のエネルギーを放つ特長をもち、正常な組織へのダメージを最小限に抑えながら、がん組織だけを狙い撃ちする。 |
| 免疫細胞療法 | 患者本人の血液から免疫細胞を採取し、体外で増やしたり活性化したりした後に再び体内に戻し、がんを攻撃する治療方法。 |
| 光線力学的療法(PDT) | がん組織に集まる性質をもった、光に反応する薬剤を投与する。薬剤が集まったところに光を当てることで活性酸素を発生させ、がんを消滅させる治療方法。 |
がんが再発する割合とリスク要因

がんが再発する割合やリスク要因について解説します。再発しやすいがんの種類についても確認しましょう。
再発しやすいがんの種類
再発しやすいがんの種類は、肺がん・大腸がん・食道がん・頭頸部がんなどが挙げられます。多くのがんは、治療終了後から2年以内に再発し、治療終了後5年を過ぎると再発リスクは大幅に低下します。しかし、乳がんは例外で、治療終了から10年以上経ってから再発することもあるのです。
がんの種類ごとの再発率
がんの再発率は、臓器や初回治療時の病期ごとに異なります。
肺がんは、再発率が高いがんの1つで、ステージ1の非小細胞肺がんであっても再発率は20%〜30%あります。
日本人における食道がんで、根治を目指した手術後の再発率は30%〜50%です。再発の種類は、局所再発が20%〜70%、遠隔再発が10%〜50%、両者を合わせた再発も7%〜27%あります。
頭頸部がんにおいて、早期がんの再発率は10%〜20%です。進行がんになると、初回治療で根治したとみられる場合でも、20%〜40%が再発するとされています。
大腸がんでは、全体の再発率は18.7%です。病期別では、ステージ1は5.7%、ステージ2は15.0%、ステージ3は31.8%と病期が進んでいるほど再発率も上昇します。
がんの再発リスクに影響を与える要因
がんの再発リスクに影響する主な要因は、初回診断時の病期とがんの性質が挙げられます。
一般に、初回診断時の病期が進んでいるほど、再発率が高くなる傾向があります。頭頸部がんや大腸がんでは、進行がんのほうが再発率が高いというデータがあります。なかには肺がんのように、ステージ1であっても再発率が比較的高いものもあるのです。
また、がんの性質も再発に影響を与えます。悪性度が高く増殖スピードの速いタイプのがんや、特定の遺伝子に対して変異があるがんでは再発しやすいとされています。
がんの再発を早期発見するための検査

がんは再発しても早期発見できると根治を目指せる可能性があります。再発がんをいち早く発見するための検査について解説しましょう。
PET-CT検査
PET-CT検査は、がん細胞が正常細胞よりブドウ糖を多く取り込む性質を利用した検査です。ブドウ糖に似た性質をもつ放射性医薬品を体内に投与し、がん細胞に取り込まれたブドウ糖の様子を画像化します。PET-CT検査は、一度の検査でほぼ全身の撮影ができ、大きさが5mm程度のがん組織を検出することも得意です。がん再発の有無のみならず、治療効果の確認にも使われます。
CTC検査
CTC検査は、血液中に流れているがん細胞(循環腫瘍細胞)を検出する検査です。がん細胞は早期のうちから血液中に放出されるため、通常の画像診断では発見できないごく小さながんを検出します。CTC検査は、少量の採血のみで全身におけるがん細胞の有無を確認できるのです。
がん再発を予防するための生活習慣

がんの再発を防ぐには、日ごろの生活習慣も改善が必要です。改善点について3つのポイントに分けてみていきましょう。
たばこや飲酒を控える
たばこやアルコールを控えることは、がんの予防につながります。
たばこの煙には発がん性物質が含まれています。喫煙すると発がん性物質が体のなかに取り込まれ、肺だけではなく、口腔・食道・胃・肝臓・膵臓など全身のがんリスクが上昇するのです。さらに受動喫煙においても発がん性があり、肺がんや乳がんのリスクを高めます。
アルコールは頭頸部・食道・肝臓・大腸・乳房など、複数のがんの原因となります。アルコールを体内で分解して生じるアセトアルデヒドが、DNAを傷つけがんを発生させるのです。
適度な運動をおこなう
適度な運動をおこなうと、男性の結腸がん・肝臓がん・膵臓がん・女性の胃がん・閉経後の乳がんのリスクを下げます。がんの再発リスクを低下させるだけではなく、がん治療中の体力や筋力の低下を防ぎ、体調を整えるためにも適度な運動は重要です。成人のがんを予防する運動量の目安として、1週間あたり150分〜300分、早足のウォーキングやサイクリングなど中等度の運動が推奨されています。
栄養バランスの良い食事をとる
がん発症リスクを下げるためには、以下の3つに注意しましょう。
- ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な野菜や果物を摂る
- 塩分は控えめにする
- 熱い飲み物や食べ物は少し冷ましてから摂る
野菜や果物をしっかり摂ることで、食道がん・胃がん・肺がんの発症リスクが低下します。
また、塩分を控えると胃がんの予防に、飲食物を冷ましてから摂ることは食道がんの予防につながるのです。
まとめ

がんが再発した場合は、まず再発後のステージ判定を受け、局所・領域・遠隔再発のどの種類か確認することが大切です。
がんの性質や全身状態に応じて、薬物療法・放射線治療・手術・緩和ケアなどから適切な治療方法を選びます。局所再発など条件によっては、根治を目指せる可能性もあります。
再発を防ぐには、たばこやお酒を控えたり、適度な運動をしたりするなど生活習慣の改善も必要です。がんの再発は稀なことではありませんが、正しい知識を持ち、定期的な検査を受けることで早期発見・早期治療につながります。不安や疑問があれば主治医に相談し、納得のいく治療を受けるようにしましょう。