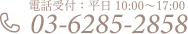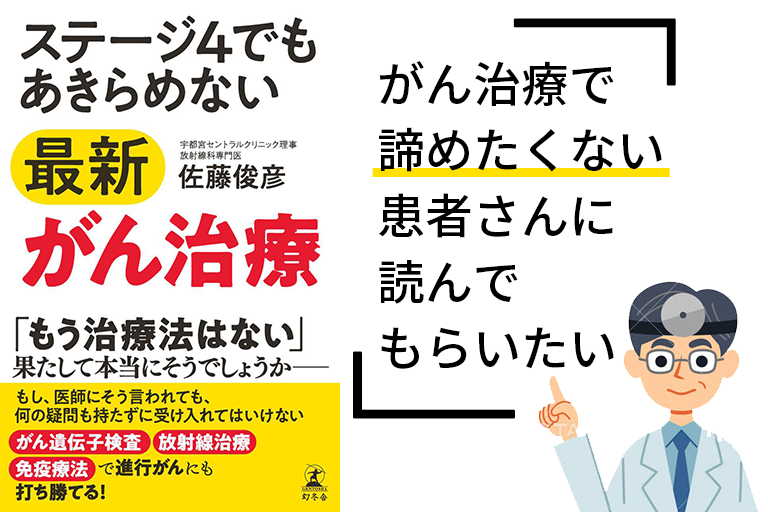8,481
8,481
がん治療におけるホルモン療法について、有効ながんの種類や費用・保険適用など解説

がん治療の選択肢の1つ「ホルモン療法」は、特定のホルモンを利用して成長するタイプのがんに効果を発揮する治療法です。本記事では、ホルモン療法が有用ながんの種類、使用する薬剤や治療期間、起こりやすい副作用などさまざまな疑問を解消します。さらに、ホルモン療法にかかる費用や保険適用についても詳しく解説します。
がん治療におけるホルモン療法とは?

がん治療におけるホルモン療法は、どのような治療であるかみていきましょう。ホルモン療法が有効ながんの種類についても解説します。
がん治療におけるホルモン療法のしくみ
がんが増殖するには、さまざまな要因が存在しています。がんの種類によっては、がん組織が成長するために、ホルモンを利用しているものがあるのです。
ホルモン療法では、がん細胞の栄養源となるホルモンが作られるのを抑えたり、ホルモンとがん細胞内にある受容体が結合するのを妨げたりして、がん細胞が成長しないようにします。
ホルモン療法が有効ながんの種類
ホルモン療法が有効である主ながんの種類について解説しましょう。
乳がん
乳がんは、全体の7割程度が女性ホルモン(エストロゲン)に依存して増えていきます。ホルモン療法の効果が得られるのは、がん細胞内にホルモン受容体がある「ホルモン受容体陽性」の乳がんです。サブタイプでは、ルミナルA・ルミナルB・ホルモン受容体陽性/HER2陽性の3つが該当します。
増殖スピードの早いルミナルBとホルモン受容体陽性/HER2陽性は、ホルモン療法とほかの薬物療法を組み合わせて治療がおこなわれます。
前立腺がん
前立腺がんは、精巣や副腎で作られる男性ホルモン(アンドロゲン)によって増殖します。ホルモン療法を積極的におこなうのは、局所進行がんや転移性がんの場合です。
限局がんであっても、高齢や合併症などの理由で、手術や放射線治療ができないときにホルモン療法が選択されます。局所進行がんの場合は、手術や放射線治療と併用することが多いです。
そのほかのがん
エストロゲンに依存して増える性質のある子宮体がんにおいても、ホルモン療法が有効です。妊娠希望がある場合や化学療法の効果が得られない場合、全身の状態が悪くほかの治療がおこなえない場合にホルモン療法が選択されます。
また、甲状腺がんのうち、乳頭がんや濾胞がんでもホルモン療法が有用です。手術後の再発や転移を予防するためにおこなわれます。
乳がんにおけるホルモン療法

乳がんにおけるホルモン療法について、治療の目的・主な治療薬・治療期間について解説しましょう。
乳がんのホルモン療法の目的
乳がんのなかには、エストロゲンを利用してがん組織を増やすタイプがあります。ホルモン療法では、エストロゲンが作られるのを抑えたり、エストロゲンががん細胞内のホルモン受容体と結合しないようにしたりして、がんが増えないようにするのです。
ホルモン受容体陽性の患者に、手術後5年間ホルモン療法をおこなうと、再発するリスクを最大で半分近くまで減らせることが分かっています。
乳がんのホルモン療法で使用する主な治療薬
乳がんのホルモン療法で使用する薬剤について、特徴や成分名を種類別に解説しましょう。
抗エストロゲン薬
抗エストロゲン薬は、がん組織のなかにあるホルモン受容体とエストロゲンが結びつくのを阻止して、がん組織が成長するのを抑える薬です。閉経前・閉経後どちらでも使用できます。抗エストロゲン薬に分類される成分には、タモキシフェン、トレミフェン、フルベストラントがあります。
LH-RHアゴニスト
LH-RHアゴニストは、卵巣内でエストロゲンが生成されるのを抑える薬です。月経のある女性ではエストロゲンは卵巣で作られているため、LH-RHアゴニストは閉経前の女性に対して使用します。分類される成分には、酢酸リュープロレリン、酢酸ゴセレリンがあります。
アロマターゼ阻害薬
アロマターゼ阻害薬は、副腎で作られるアンドロゲンがエストロゲンに変換するときにかかわる酵素を阻害して、がんが増えるのを抑える薬です。閉経を迎えると卵巣が働かなくなり、代わりに副腎で作られるアンドロゲンからエストロゲンが生合成されます。
そのため、アロマターゼ阻害薬は閉経後の女性に使用します。分類される成分は、アナストロゾール、レトロゾール、エキセメスタンです。
乳がんにおけるホルモン療法の治療期間
乳がんのホルモン療法は、手術後の初期治療として使用することで再発や転移を防ぎます。術後少なくとも5年以上の継続服用が必要です。
近年の研究報告によると、術後5年以上経ったあとでも再発するケースがあるため、効果と副作用のバランスを考慮しながら、ホルモン療法を術後5年〜10年の長い期間おこなうことが推奨されています。
前立腺がんにおけるホルモン療法

前立腺がんにおけるホルモン療法について、特徴・主な治療薬・治療期間について解説しましょう。
前立腺がんのホルモン療法の特徴
前立腺がんは成長するのに、男性ホルモンのアンドロゲンを利用しています。ホルモン量が多いほど増えるため、ホルモン療法ではアンドロゲンが作られるのを抑えたり、アンドロゲンがホルモン受容体と結びつくのを抑えたりして、がん細胞が増えないようにするのです。
前立腺がんのホルモン療法は、がん組織を小さくすることはできますが、死滅させることは難しく、長い間治療を続けていると次第に効果が弱くなることが分かっています。
前立腺がんのホルモン療法で使用する主な治療薬
前立腺がんのホルモン療法で使われるについて、特徴や成分名を種類別に解説しましょう。
LH-RHアゴニスト
LH-RHアゴニストは、LH-RH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)によく似た構造を持つ薬剤で、脳の下垂体にあるホルモン受容体に結合します。薬剤を投与し続けると、次第に下垂体のホルモン受容体が反応しなくなることで、結果的に精巣で作られるテストステロン量が減り、がんの増殖を抑えるのです。
LH-RHアゴニストに分類される成分には、酢酸リュープロレリン、酢酸ゴセレリンがあります。
LH-RHアンタゴニスト
LH-RHアンタゴニストは、脳の下垂体にあるホルモン受容体をダイレクトに阻害する薬です。下垂体から精巣へホルモンを生成する命令が届かなくなり、テストステロンの産生を抑えます。分類される成分には、デガレリクス酢酸塩があります。
抗アンドロゲン薬
抗アンドロゲン薬は、テストステロンが作り出すDHTというタンパク質が、前立腺がんの細胞内にあるアンドロゲン受容体と結びつくのを阻止する薬です。がん細胞に対するテストステロンの働きを抑えることで、がんが成長するのを抑えます。分類される成分には、ビカルタミド、フルタミドがあります。
新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬(ARSI)
新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬(ARSI)は2種類あります。
1つは、アンドロゲンががん細胞にある受容体に結びつくのを妨げ、さらに受容体を介したシグナル伝達も阻害する薬です。こちらに分類される成分には、アパルタミド、エンザルタミド、ダロルタミドがあります。
もう1つは、アンドロゲン合成酵素の働きを妨げることで、アンドロゲンが作られないようにする薬です。こちらに分類される成分には、アビラテロンがあります。
女性ホルモン薬
女性ホルモン薬を使用すると、精巣を刺激するホルモンの分泌を抑えて、結果的に男性ホルモンの分泌量を減らせます。ほかのホルモン療法で効果がみられないときに選択します。前立腺がんで使用する女性ホルモン薬には、エストラサイト、プロセキソールがあります。
前立腺がんにおけるホルモン療法の治療期間
前立腺がんにおけるホルモン療法の治療期間は、おこなうタイミングやリスク分類によって異なります。
放射線治療と併用する場合の治療期間は、中リスク群で6ヶ月、高リスク群で2年~3年です。
年齢や合併症などで手術や放射線治療ができない場合・転移がみられる場合で、ホルモン療法をおこなうケースでは、定められた治療期間はなく、できるだけ長く継続します。
がんのホルモン療法における副作用と対処法

がんのホルモン療法で起こりやすい副作用とその対処法について解説しましょう。
乳がんホルモン療法の主な副作用と対処法
乳がんのホルモン療法でよくみられる3つの副作用について、対処法とともに解説します。
更年期様症状
ホルモン療法をおこなうと体内のエストロゲン量が少なくなるため、ほてりやのぼせ、動悸などの更年期によく似た症状がおこりやすくなります。治療を継続していくと、次第に軽減することが多くみられます。
自分でおこなう対策として、体温を調節しやすい服装を取り入れたり、自律神経を整えるために運動をおこなったりすると良いです。日常生活に支障があるほど症状が重い場合は、一部の抗うつ薬や抗てんかん薬、漢方薬で対応できるため、医師に相談しましょう。
子宮や膣の症状
エストロゲン量の低下により、性器出血・膣の分泌物の増加・膣の乾燥などがみられます。閉経後乳がんの場合、タモキシフェンの服用により、子宮体がんの発症リスクが上昇しますが、乳がんの再発を防ぐ効果のほうが大きいです。タモキシフェン服用中に不正出血が生じた際は、婦人科を受診して精密検査を受けるようにしましょう。
骨や関節の症状
アロマターゼ阻害薬の服用により、骨粗しょう症や関節の痛み・こわばりが起こりやすくなります。骨粗しょう症対策として、日常生活ではカルシウムやビタミンDの多い食品を摂る・適度に運動をする・日光を浴びるなどの対策をおこないましょう。骨密度が低い場合は、ビスホスホネート製剤や抗RANKL抗体薬で治療することがあります。
前立腺がんホルモン療法の主な副作用と対処法
前立腺がんのホルモン療法でおこりやすい副作用とその対処法について解説しましょう。
ホットフラッシュ
発症のメカニズムは解明されていませんが、治療により男性ホルモン量が低下することで、ほてりやのぼせといったホットフラッシュが起こりやすくなります。治療を継続するうちに症状が気にならない程度になることもありますが、日常生活に支障をきたす場合は漢方薬・抗うつ薬のSSRI・エストロゲン製剤などで治療をおこなうことがあります。
性機能障害
ホルモン療法では、性機能障害がおこりやすくなります。治療中に改善することは難しいですが、ホルモン療法中止後に症状は徐々に改善します。
ただし、ホルモン療法の種類や服用量によっては、回復までに半年程度かかることがあるのです。PDE5阻害薬の服用や血管拡張剤の注射などで、勃起機能の回復は期待されていますが、性欲の低下については改善できないため注意しましょう。
骨粗しょう症
アンドロゲンには骨を丈夫にする作用もあるため、ホルモン療法で長期的に量を低下させると、骨粗しょう症を発症しやすくなります。日常生活では、カルシウムやビタミンDを十分に摂取する・適度に運動をする・日光に当たるなどの対策をおこないましょう。生活習慣を改善しても骨密度の低下がみられるときは、ビスホスホネート製剤・抗RANKL抗体薬で治療をおこなうことがあります。
糖脂質代謝障害
ホルモン療法でアンドロゲン量が少なくなると、筋肉量が減り、内臓脂肪がつきやすくなります。それにより、心血管疾患を引き起こすこともあるのです。
日常生活における対策として、適度な運動をおこない、バランスの良い食事を心がけましょう。血圧・血中脂質・血糖のコントロールが難しい場合は、降圧剤・スタチン剤・血糖降下薬などで治療をおこないます。
がんのホルモン療法で保険適用される薬剤と治療費用
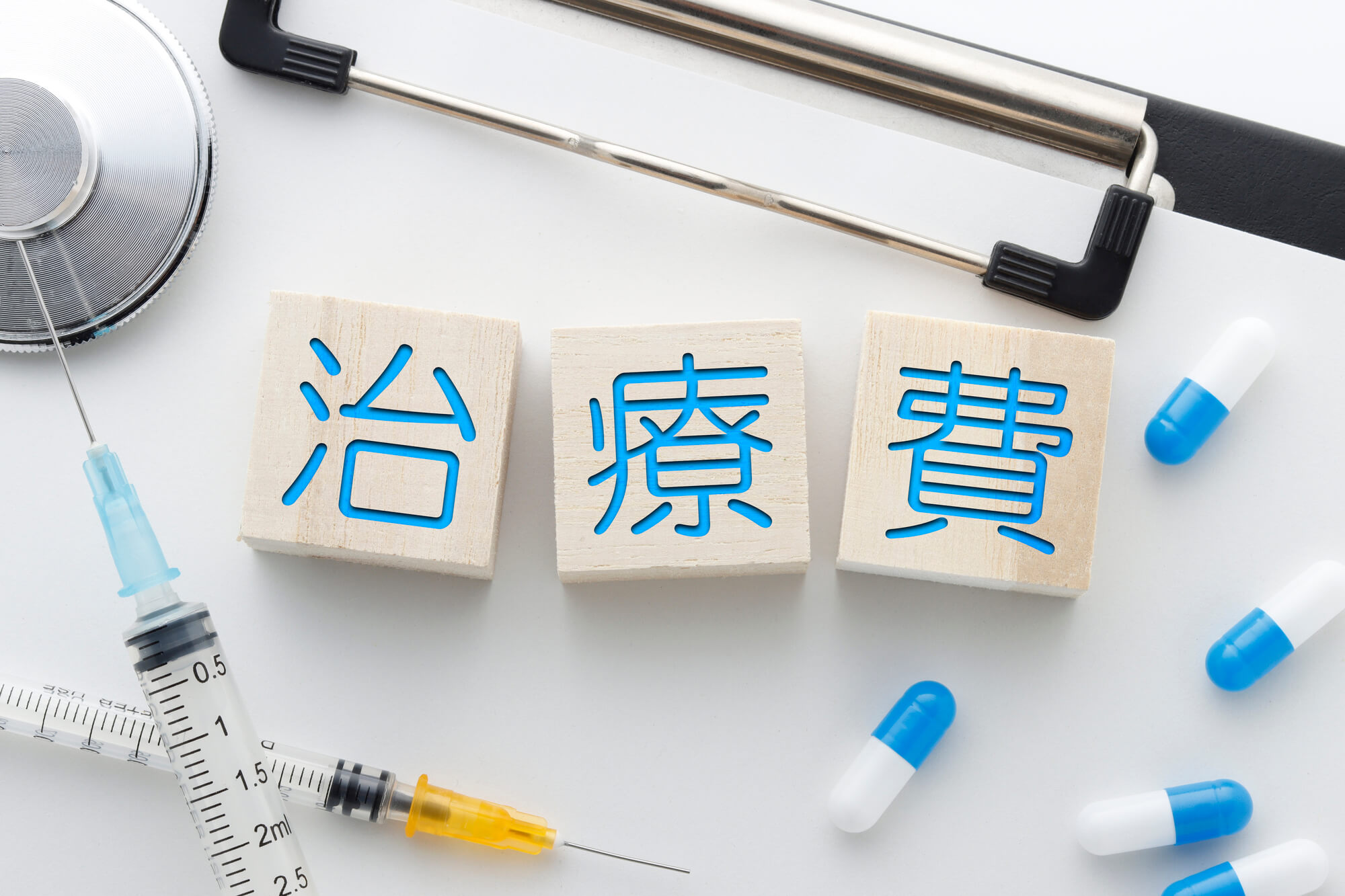
がん治療におけるホルモン療法は、保険適用されています。治療費が高額になり支払いの負担が大きい場合は、高額療養費制度を利用しましょう。自己負担額の上限を超えた分について払い戻しされます。
以下より、がんの種類ごとに使用する薬剤とその治療費について解説しましょう。
乳がん
乳がんで保険適用される薬剤と薬剤費は以下のとおりです。治療費を支払う際には、診察代や技術料などが加わります。一部の薬剤については、ジェネリック医薬品を使用すると費用が軽減されます。
| 薬剤名 | 1年間の総額 | 自己負担額 (3割負担の場合) | |
|---|---|---|---|
| 抗エストロゲン薬 | タモキシフェン | 約3万円~6万円 | 約1万円~2万円 |
| トレミフェン | 約6万円~17万円 | 約2万円~5万円 | |
| フルベストラント | 約100万円 | 約30万円 | |
| LH-RHアゴニスト | 酢酸リュープロレリン | 約13万円~18万円 | 約4万円~5.4万円 |
| 酢酸ゴセレリン | 約15万円~30万円 | 約4.5万円~10万円 | |
| アロマターゼ阻害薬 | アナストロゾール | 約6万円 | 約1.8万円 |
| レトロゾール | 約8万円 | 約2.4万円 | |
| エキセメスタン | 約7万円 | 約2万円 |
前立腺がん
前立腺がんで保険適用される薬剤と薬剤費は以下のとおりです。治療費を支払う際には、診察代や技術料などが加わります。一部の薬剤については、ジェネリック医薬品を使用すると費用が軽減されます。
| 薬剤名 | 1年間の総額 | 自己負担額 (3割負担の場合) | |
|---|---|---|---|
| LH-RHアゴニスト | 酢酸リュープロレリン | 約13万円~18万円 | 約4万円~5.4万円 |
| 酢酸ゴセレリン | 約15万円~30万円 | 約4.5万円~10万円 | |
| LH-RHアンタゴニスト | デガレリクス酢酸塩 | 約27万円 | 約8万円 |
| 抗アンドロゲン薬 | ビカルタミド | 約6.5万円 | 約2万円 |
| フルタミド | 約13万円 | 約4万円 | |
| 新規アンドロゲン受容体シグナル阻害薬(ARSI) | アパルタミド | 約300万円 | 約90万円 |
| エンザルタミド | 約300万円 | 約90万円 | |
| ダロルタミド | 約300万円 | 約90万円 | |
| アビラテロン | 約530万円 | 約160万円 | |
| 女性ホルモン薬 | エストラサイト | 約15万円 | 約4.5万円 |
| プロセキソール | 約3万円~6万円 | 約1万円~1.8万円 |
まとめ

ホルモン療法は、乳がんや前立腺がんなど特定のホルモンを利用して成長するがんに対して有用な治療です。乳がんではエストロゲン、前立腺がんではアンドロゲンを標的とした薬剤が使用され、治療期間はがんの種類やリスクによって異なります。
ホットフラッシュや骨粗しょう症などの副作用が起こりやすくなりますが、適切な対処法でコントロール可能です。ホルモン療法で使用する薬剤は保険適用され、高額療養費制度を利用すると経済的な負担を減らせます。
ホルモン療法は年単位にわたる可能性もあるため、治療のメリットとデメリットを理解した上で、納得のいく選択をしましょう。