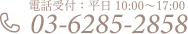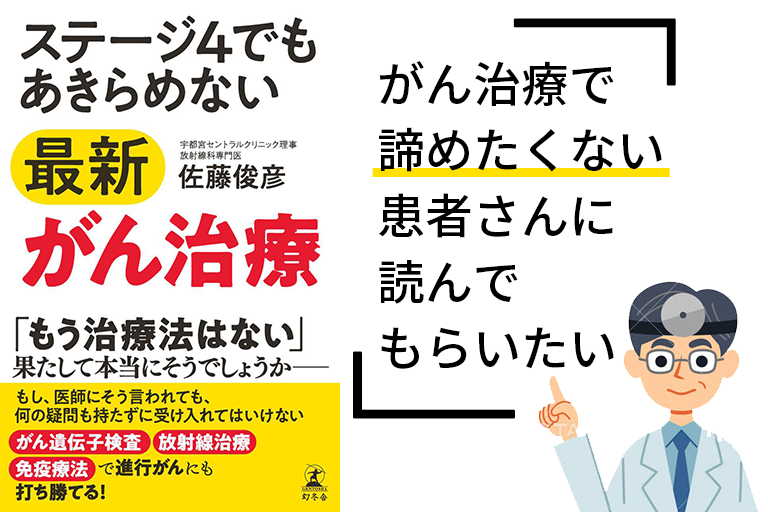4,257
4,257
余命宣告されてもがんは治る?余命の判断基準や宣告のタイミングなど解説

がんと診断されて日々治療と向きあっている患者さんやご家族にとって、医師から余命を宣告されるのはとてもつらいことです。しかし、医師がどのような判断基準で余命を宣告するのか、また、宣告の内容はどこまで信頼できるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、余命宣告の判断基準やタイミング、宣告されたらするべきことや宣告後の治療の選択肢について詳しく解説していきます。がんの治療をされている方や、ご家族ががんで闘病されているという方はぜひご一読ください。
目次
余命宣告とは

余命宣告とは、医師から患者さんや家族の方に対して「あとどれくらい生きられるか」という余命の期間を伝えることです。
一般的に余命宣告は、がんをはじめとした重い病気の患者さんにおこなわれることがほとんどです。なかでも、進行性のがんは治療にともなう合併症などのリスクが高いため、治療前にあらかじめ余命が告げられることもあります。
しかし、余命宣告には明確な予測の手順やルールは存在しません。余命は、患者さんの病状や過去のデータをもとに医師が予測した数値であり、目安でしかないのです。そのため、「6か月」や「2年」と言われることもあれば、「2年から3年」と幅をもたせて宣告されるケースもあります。
特に、がんは人によって進行状況や治療法がそれぞれ違うため、将来の予測が難しい病気でもあります。余命は「寿命」とは異なり、あくまでも目安の期間であることを理解しておきましょう。
余命宣告の判断基準

前述のとおり、余命宣告に明確なルールは存在しません。そのため、どのように余命を判断するのか、医師によってその基準も異なります。ここでは、余命を予測・判断する際に使用されているデータの代表的なものとして、「生存期間中央値」と「5年相対生存率」について解説していきます。
生存期間中央値
「生存期間中央値」とは、同じタイプ・進行度のがんに対して、同じ治療をおこなった患者さんの50%が亡くなるまでの期間を示す数値です。
たとえば、99人の患者さんのデータがある場合、生存期間の長い人から短い人までを順に並べ、ちょうど中央になる50番目の人のデータを生存期間中央値とします。「この治療をおこなった場合、余命は○年」と宣告されるケースでは、医師が生存期間中央値を根拠に判断していると考えられます。
しかし、気をつけなければならないのは、がんのタイプと進行度が同じで同様の治療法を選択したとしても、宣告された余命の前に亡くなる人もいれば、長く生きられる人もいるということです。がんという病気はとても複雑で、それぞれの患者さんの状態やがんの性質によって余命にも違いがあらわれることを覚えておきましょう。
5年相対生存率
国立がん研究センターが発表している「5年相対生存率」も、医師が余命の予測に用いるデータとして一般的です。
5年相対生存率とは、「がんだと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いか」を示す数値です。「がんの診断を受けてから5年以上生きられる割合」ではないので注意しましょう。
また、この数値は「診断されてから5年」であることもポイントのひとつです。がんを診断されるタイミングはそれぞれ違います。人間ドックなどで早期に発見・診断されることもあれば、診断時にはすでに進行していたということも考えられます。5年相対生存率は、これらすべてのケースを対象として算出されていることを考慮しましょう。
余命宣告はどれくらい正確なのか?
ここまで、生存期間中央値と5年相対生存率について解説してきましたが、いずれも過去のデータをもとにした統計値であることをご理解いただけたと思います。
医師は過去の症例で得た経験から、これらのデータに加え、がんの進行状況やおこなってきた治療への反応、合併症のリスクなどを総合的に判断して余命を宣告します。しかし、将来的な治療の効果や経過を予測することは非常に難しいことです。したがって、余命宣告は必ずしも正確ではなく、目安として考えたほうがよいといえるでしょう。
余命宣告のタイミング
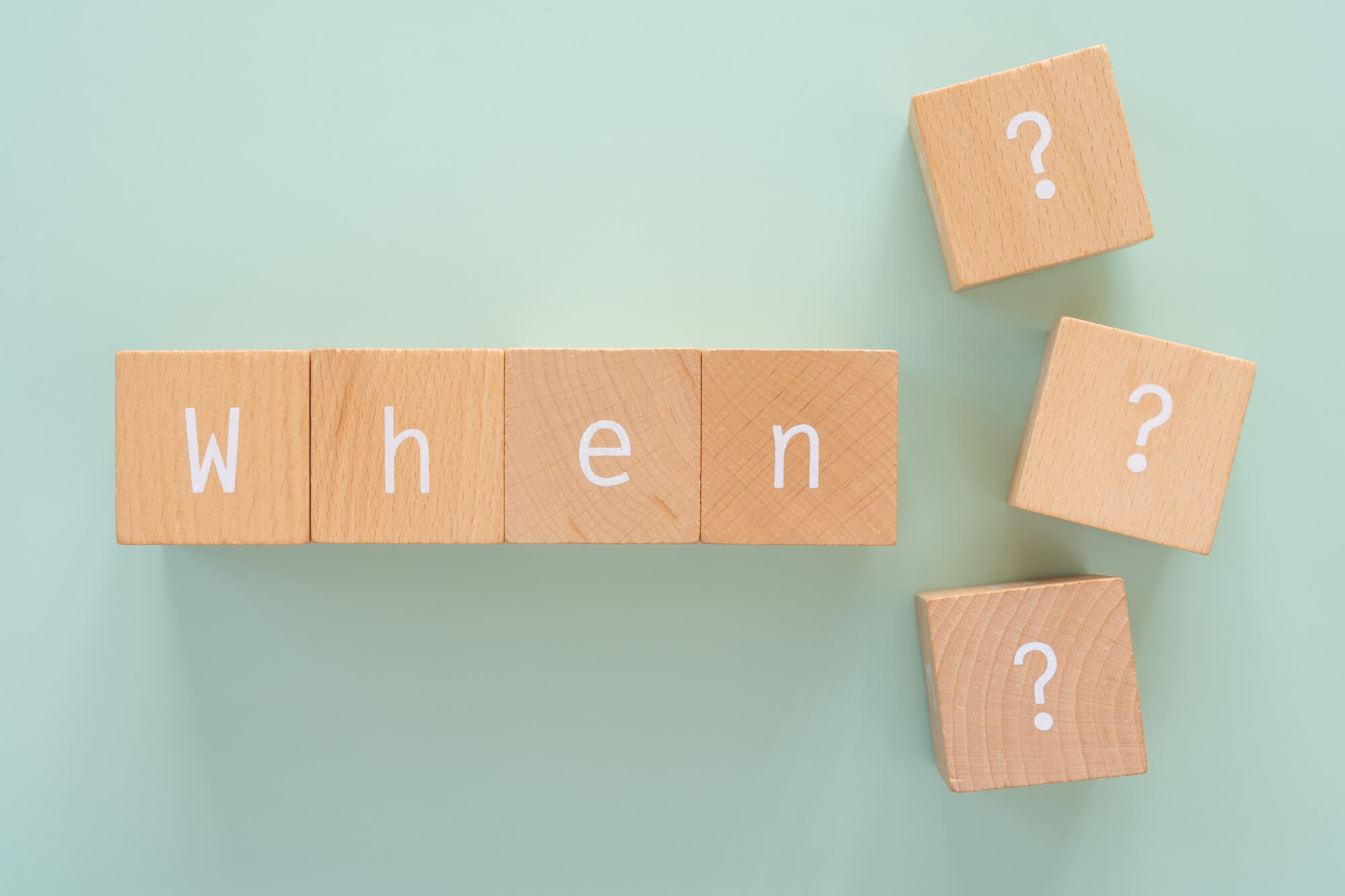
がんの余命宣告は、これ以上は「標準治療」を用いての治療ができないと判断されたときにおこなわれることが一般的です。
標準治療とは、手術・抗がん剤治療・放射線治療の3つの治療方法を指します。多くの場合、それぞれのがんの種類や進行度・病状などから、これら3つの治療を組み合わせて治療をおこないます。
しかし、がんが進行して手術ができない、抗がん剤に効果が認められなくなったなど、これ以上の標準治療では回復が望めなくなったときに医師によって余命が宣告されます。また、治療方法がまだ残されていたとしても、患者さんが高齢であったり、体力的に治療の副作用に耐えられないであろうと判断されたりした場合は余命を宣告されることがあります。
しかし、いずれの場合も、医師が治療に手を尽くしたうえで余命を宣告するという点では一致しています。余命宣告は、決して医師が治療をあきらめたということではなく、患者さんが残された時間をどのように過ごしていくのかを問うものであるという一面もあるのです。
余命宣告をされたらするべきこと

ある日突然に医師から余命を宣告されたら、患者さんやご家族はその事実を受け入れるだけでも心に大きな負担を感じることでしょう。しかし、前述のとおり「余命=寿命」ではありません。患者さんやご家族が残された時間を悔いなく過ごすためにも、余命宣告後には決断しなければならないことや乗り越えなければならないことがあります。ここでは、余命宣告を受けたあとにするべきことについて説明していきます。
今後の治療方針を選択する
余命宣告後は「余命の期間をどのように過ごすのか」決断することが求められます。いちばんのポイントとなるのは今後の治療方針ですが、医師からいくつかの選択肢が提示されることが一般的です。余命宣告後の治療方針の選択肢には、おもに以下の4つが挙げられます。
- 完治を目指す
- 延命治療をおこなう
- 緩和ケアに移行する
- セカンドオピニオンを受ける
これらの選択肢から治療方針を決めるにあたっては、これまでの治療の経過や現在の病状、今後どのように病気が進んでいくのか医師から説明を受け、疑問や不安があれば必ず確認しておくようにしましょう。そして、状況をしっかりと理解したうえで家族とも話し合い、最終的には患者さん本人が望む方法を選択することが大切です。それぞれの選択肢については、後ほど詳しく解説していきます。
患者さん本人・家族の心のケア
余命宣告は患者さんやご家族に大きなショックを与えます。しかし、残された時間を有意義なものにするためには、このショックを乗り越えなければなりません。そのため、余命宣告を受けた患者さん本人はもちろんのこと、ご家族の心のケアにも配慮することが必要となります。
余命宣告をどのように受け止めるかは患者さんによって異なりますが、宣告後の精神面は以下のような経過をたどっていきます。
- 第1期:衝撃の時期
- 第2期:不安と抑うつの時期
- 第3期:適応の時期
「衝撃の時期」と「不安と抑うつの時期」はそれぞれ1週間ほど続くといわれています。この時期は、患者さん本人がショックを受け止めきれないため、家族や周囲の人に怒りや悲しみの感情をぶつけてしまうことがあります。困難な時期ではありますが、ご家族が状況を理解し、寄り添う姿勢をあらわすことで患者さんの心も徐々に安定し、「適応の時期」へと移行していきます。
一方で、患者さんのケアをするご家族にも精神的・肉体的ストレスが蓄積していくでしょう。「本人がいちばんつらいのだから」と患者さんを最優先にし続けていると、ご家族の健康状態やメンタルにも不調があらわれる恐れがあります。ときには周囲の人に助けを求め、患者さんのケアから少し距離をおくことも大切です。
たとえば、全国のがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院には「がん相談支援センター」が設置されており、その病院で診療を受けていなくても利用することが可能です。
相談員として専門の看護師やソーシャルワーカーが対応にあたっており、患者さん本人だけではなく、ご家族でも相談することができます。「余命宣告を受けてつらい」「どうしていいかわからない」といった漠然とした悩みであっても聞いてもらえるため、安心して利用していただけます。
余命宣告後の治療の選択肢

前述のとおり、余命宣告後の治療の選択肢として「完治を目指す」「延命治療をおこなう」「緩和ケアに移行する」「セカンドオピニオンを受ける」の4つが挙げられます。ここでは、それぞれの選択肢について詳しく解説していきます。
完治を目指す
標準治療である手術・抗がん剤治療・放射線治療の3つの治療方法についてはすでに説明してきましたが、近年、第4の治療方法として「免疫療法」が注目を集めています。
これまで、標準治療の継続が難しいと判断された場合、完治の見込みはないとして延命治療か緩和ケアのどちらかを選択することが一般的でした。しかし、免疫療法をおこなった結果、これ以上標準治療はできないと診断されたケースでも寛解にいたったという報告がされています。(寛解:病気の症状や検査の異常が消失した状態)
同じように、免疫治療と放射線治療を組み合わせた「免疫放射線治療」も、標準治療の適応ではなくなった患者さんに有効だといわれています。
免疫放射線治療における免疫治療では、免疫ががん細胞を攻撃する力を維持する「免疫チェックポイント阻害剤」が使用されます。この免疫チェックポイント阻害剤と放射線治療を併用することで、全身に転移しているがんに対しても効果を発揮することがわかってきています。
以上のように、がんの余命宣告をされたとしても完治する可能性はゼロではなく、「まだ治療をあきらめられない」という患者さんには、完治を目指すという選択肢も残されているといえるでしょう。
ただし、治療方法によっては保険が適用されず、高額の医療費が必要になる場合があるため、経済的な面も考慮して検討することが必要です。
延命治療をおこなう
延命治療とは「寿命」を延ばすためにおこなわれる治療のことで、完治を目指すものではありません。たとえば、「子どもの卒業式に出席したい」「もう一度故郷を訪れたい」など、数か月のうちに予定されている行事に参加するために延命治療を選択するといったケースが多いようです。
延命治療では、患者さんの希望する時期までの延命を実現するために手術や投薬などの積極的治療をおこなうことがあります。そのため、病院で過ごす時間が長くなる可能性があることも理解したうえで決断する必要があります。
緩和ケアに移行する
緩和ケアは、がんにともなう身体的・精神的な苦痛を和らげ、QOL(Quality of Life=生活の質)を維持することを目的としておこなわれます。
緩和ケアは、終末期ケアと間違われることがよくあります。苦痛を取り除きQOLを維持するという点では、緩和ケアも終末期ケアも同じだといえます。しかし、終末期ケアは、患者さんが自分らしい最期をむかえるためのサポートをすることがいちばんの目的です。
一方緩和ケアは、まだできる治療があればその治療の苦痛を和らげたり、精神的な不安を取り除いたりと、患者さんが前向きに安心してがんと向きあえるようにサポートすることを目的としています。そのため、余命宣告後だけではなく、がんと診断されてからすぐに緩和ケアを選択する患者さんも少なくありません。
緩和ケアを受ける方法としては、「通院」「入院」「在宅」の3つの選択肢があります。がん診療連携拠点病院であれば全国どこでも受けることができますが、それ以外にも緩和ケア外来や緩和ケア病棟を設置している病院や、緩和ケアを専門としている病院もあります。患者さんの希望する方法・病院で緩和ケアを受けることができればベストではありますが、病状やご家族のサポートの範囲、費用の面もトータルで検討することが大切です。
セカンドオピニオンを受ける
宣告後の治療方針を決めるにあたり、主治医からの説明だけでは判断しきれないという場合は、セカンドオピニオンを受けることも選択肢のひとつとなります。
セカンドオピニオンとは、主治医以外の医師に病気の診断や治療方法についての意見を求めることです。主治医を変えたり、転院したりすることを目的とするものではなく、あくまでも違う医師の見解を知るためにおこないます。
現在は医師の専門分野も細分化が進んでいるため、必ずしも医師がすべての治療方法について熟知しているわけではありません。そのため、セカンドオピニオンを受けることで、主治医の方針とは違う新たな治療方法を提案してもらえる可能性があります。
余命を宣告されたタイミングでセカンドオピニオンを受けることは、これまでの診断や治療を振り返り、今後の治療方針を決めるうえで非常に有意義であるといえます。現在、多くの病院がセカンドオピニオン外来を設けていますので、余命宣告に納得できない、治療をあきらめたくないという方にはセカンドオピニオンの受診をおすすめします。
まとめ
余命宣告とは、医師が「あとどれくらい生きられるのか」という期間を患者さんやご家族に伝えることです。余命宣告には明確なルールや予測の手順はなく、医師によって判断の基準も異なります。そのため、余命は必ずしも正確ではなく、あくまでも目安でしかないといえます。
がんの余命宣告は、標準治療を続けることができないと判断されたタイミングでおこなわれることが多く、宣告後は今後の治療方針を決めることが求められます。
おもな治療方針として、「完治を目指す」「延命治療をおこなう」「緩和ケアに移行する」の3つが挙げられますが、悔いのない決断をするためには「セカンドオピニオンを受ける」ことも選択肢のひとつとなります。
近年は、転移などにより標準治療の適応がないと余命宣告されたケースでも、第4の治療法である免疫療法による治療の効果が数多く報告されています。余命を宣告されてもすぐに治療をあきらめるのではなく、セカンドオピニオンで新たな治療方法の可能性について意見を求めることは非常に有意義であるといえるでしょう。