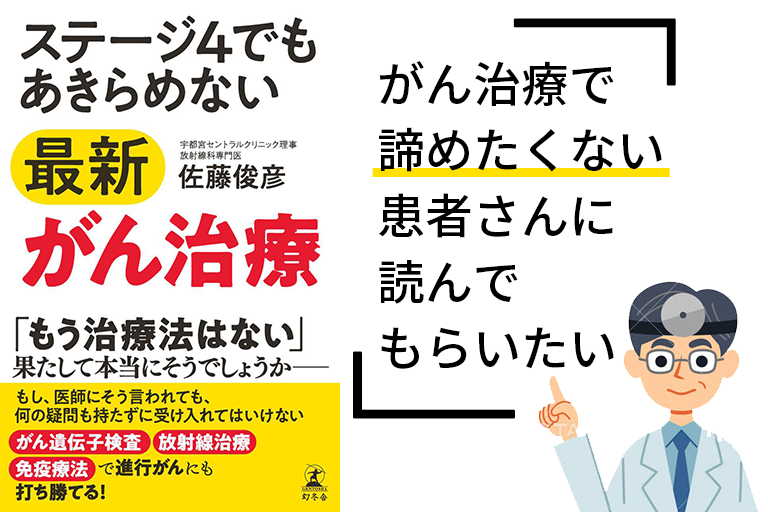113
113
がん画像診断の最新機器PETの仕組み・課題・今後の可能性とは?
がんの診断に使われる画像診断機器の使命は、より正確に、より精密にがんを可視化することです。
正確な画像はより安全な治療を実現するのに役立ちますし、精密な画像は小さながんの発見につながります。
今回取り上げる画像診断機器・検査は「PET」です。
PETではがん細胞に目印をつけて撮影することでがんを可視化します。
PETの詳しい仕組み、CTやMRIとの違い、そしてPETの抱える課題についてみてみましょう。

PETは他の画像診断機器と何が違うの?
がん診断で使われる画像診断機器と言えばCTやMRIが有名ですね。
「PETも似たようなものなのでは?」そう思われる方もいるかもしれません。
しかし、PETとCT、そしてMRIは根本的に考え方の違う画像診断検査です。

CTとMRIは「形態診断」です。撮影した画像に写った形の異常からがんの有無が判断されます。
一つひとつの小さな影が、果たしてがんなのか、そうではないのかは、診断する医師が見極めなければなりません。
大きながんであれば、まず間違えることはないでしょうが、小さながんであれば見逃されることもあるかもしれないのが難点です。
一方、PETは、がん細胞そのものを目立たせて撮影する「機能診断」の画像診断検査です。
その細胞がどの程度FDG(詳しくは後述)を取り込んでいるのかという活発具合から、がんか否かをはかります。
がん細胞が自ら「私はがんです」と手を挙げているようなもので、小さな病変も発見しやすいのがこのPETの特徴です。
PETがなぜ小さながんまで発見できるのか、詳しく説明しましょう。
PETの詳しい仕組み
PETはPositron Emission Tomographyという英語の頭文字をとった略語で、日本語では「陽電子放射断層撮影法」と呼ばれる検査です。
最近はPETとCTが一体化した「PET/CT」が一般的になっているため、PETといえばPET/CTを指すこともあります。
PETでは、ブドウ糖によく似た「18F-FDG」という薬を使います。
FDGはブドウ糖と似た薬剤そのものの名前、そして18Fは「放射性フッ素」のことを指します。
18F-FDGはつまり、放射性フッ素で標識したFDGという意味になります。

がん細胞は、正常な細胞溶離活動が活発で、エネルギー源としてブドウ糖を大量に取り込みます。これを「ワールブルク効果」と言います。
PETでは、18F-FDGを静脈から注射します。すると、ワールブルク効果で、がん細胞はブドウ糖と間違えてこの薬を取り込みます。
この状態を撮影すると、18F-FDGを大量に取り込んだがん細胞がハッキリと写ります。5㎜程度のがんでも認識できるほどです。
PETの抱える課題
優秀な検査として注目されているPETですが、オールマイティというわけではなく、少々課題を抱えているのも現実です。
特に弱点とされるのが、糖が多く存在する臓器における診断です。
糖を多く代謝する脳や心筋、糖を排泄する通り道となる尿路(腎盂、尿管、膀胱)などの臓器では、がん細胞でなくともFDGが多く集まってしまいます。
これでは、その臓器や周辺のがんを目立たせることはできません。
また、活発に動いていないがんも画像に写りにくいものです。
早期がんの中には、活動が少なく、画像判別が難しいものもあるのが現状です。
PETが最適とは言えないがんでは、CTやMRIなど別の画像診断機器も使って診断を行う必要があります。

まとめ
画像診断の正確性や精密度は確実に上がってきています。
がんの治療に最も大切なのが早期発見・早期治療です。いかに小さいうちにがんを見つけ、治療を始められるかどうかが、患者さんの人生を左右します。
早期発見さえできれば、がんの完治は夢ではありません。
日本はまだまだがん検診の受診率が低いですね。
ほんの少しでも不安のある方はぜひ定期的にがん検診を受けるようにしましょう。