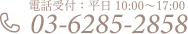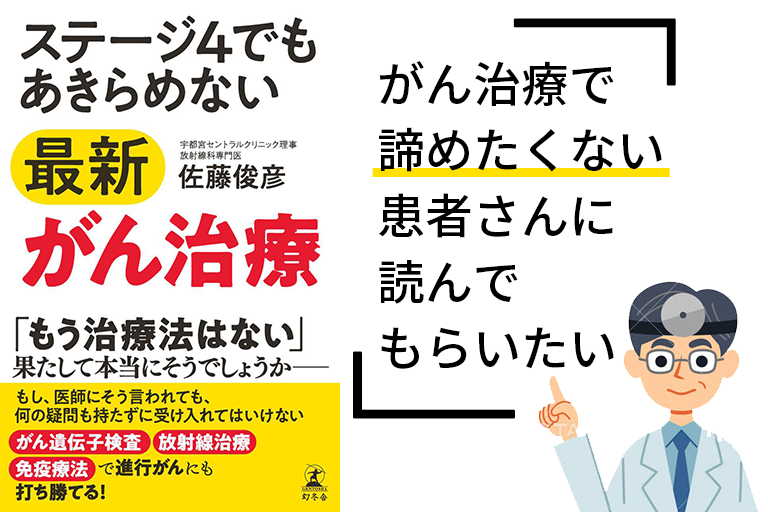417
417
入院中にセカンドオピニオンは受けられる?家族が代理で相談できる?

主治医から病状や治療法を提示されたとき、セカンドオピニオンを受けたいと思う患者さんや家族は少なくありません。ただし、入院中ですでに治療が始まっていたり、自由に外出できない状況だったりする場合、「入院中でも受けられるのか」「家族が代わりに相談できるのか」といった疑問を持つ人もいるでしょう。
この記事では、入院中にセカンドオピニオンを受ける時期や具体的な流れ、家族による代理相談の方法、オンライン受診の活用法まで詳しく解説します。
目次
入院中におけるセカンドオピニオンについて

セカンドオピニオンの意味や、入院中に必要となるケースなどについて解説します。
そもそもセカンドオピニオンとは
セカンドオピニオンの目的は、主治医とは異なる医療施設の中立的な立場の医師から、病気の診断や治療法にかかわる見識を聞き、自分にとって適切な治療法を選ぶことです。
セカンドオピニオンはアドバイスを求める場であり、現時点の医療施設や主治医を変更することが目的ではありません。 セカンドオピニオンは健康保険の適用外となるため、費用は全額自己負担となります。
入院中の患者がセカンドオピニオンを受ける権利
患者さんは、自分の病状や治療法についてさまざまな見識を聞き、希望する治療を決定する権利があります。入院中の患者さんがセカンドオピニオンを望む場合も、遠慮せず主治医に申し出ましょう。
入院中にセカンドオピニオンを受けるときは、主治医に今までの治療経過や検査結果など資料の作成をお願いします。今までの治療にかかわる資料は、セカンドオピニオンを受け持つ医師が客観的に評価し、適切なアドバイスをおこなう上で欠かせないものとなります。
入院中にセカンドオピニオンが必要となるケース
入院している際にセカンドオピニオンを求めるケースは多岐にわたります。
提示された病状・治療法について気がかりなことがあった場合に、中立的な立場の医師から主治医と異なる視点で見識を聞くと理解が深まり、治療法の決定に役立つでしょう。 主治医から提示された治療以外の方法がないか知りたい場合など、セカンドオピニオンによって、新たな治療法が見つかる可能性があります。
がんのように治療法が専門的で長引く状況では、現在おこなっている治療の評価や治療法を見直すときに、中立的な立場の医師から見識を聞き、納得して治療に臨めることもあります。
入院中にセカンドオピニオンを受ける時期

入院中にセカンドオピニオンを検討する場合の、適切な時期について解説します。
適切なタイミングの見極め方
入院中にセカンドオピニオンを受ける適切な時期は、主治医から診断が下りたり治療法を提案されたりした時点です。治療を開始した後には、ほかの治療を希望しても切り替えるのが難しくなる可能性があります。診断が下りて治療法を検討する段階や、病状の進行などにより治療法を見直す必要が生じた時点でセカンドオピニオンを活用しましょう。
緊急性のある治療との兼ね合い
病状によっては、セカンドオピニオンに時間をかけることが難しいケースがあるため、緊急性のある治療との兼ね合いを考慮しましょう。 病状の進行度によっては、すぐに治療を始めたほうが良いケースもあるため、セカンドオピニオンを検討する際は、いつまでに結果を出せばよいか主治医へ確かめることが大切です。
病状が急速に進行する可能性のある場合、セカンドオピニオンに時間をかけすぎると、状況が悪化し、治療の選択肢がかえって狭まるリスクがあります。主治医が早期の治療開始を勧める理由をきちんと理解し、その上でセカンドオピニオンの必要性を考えましょう。
病状の安定期に受けるメリット
病状が比較的安定している時期であれば、焦ることなく治療法を考えることができます。主治医からの説明に加えて、ほかの医師から見識を聞くことで、病状や治療に対する理解が深まり、納得のいく治療を受けることにつながります。さらに、セカンドオピニオンで質問したいことを精査する時間が十分に持てるため、限られた相談時間を有効活用し、自分が知りたい情報を得られる可能性が高くなります。
入院中にセカンドオピニオンを受診する流れ

入院中にセカンドオピニオンを受ける際の流れを、4つのポイントに分けて解説します。
①現在の主治医から病状や治療法について十分な説明を受ける
セカンドオピニオンは、自分の納得のいく治療法を選ぶために、主治医以外の中立的な立場の医師からアドバイスを求める制度です。主治医の提案とほかの医師からの見識を比較するために、まずは主治医からの説明を十分に理解しておきましょう。
主治医から提示された病状や治療法について、その理由を含めて理解できるまで説明してもらうことが大切です。分からない点があれば遠慮せずに質問し、メモを取ったり家族と一緒に説明を聞いたりします。主治医の意見をきちんと理解することで、疑問に感じることや詳しく知りたいことが明確になります。
②セカンドオピニオンの希望を伝える
入院中でも躊躇せず、主治医にセカンドオピニオンを望むことを申し出ましょう。主治医に対して「説明してもらった内容について、自分でも情報を集めて納得のいく治療をしたい」という意思をきちんと伝えることが大切です。
患者本人が高齢であったり15歳未満の子どもであったりして判断能力が不十分な場合、または入院中で直接話を聞くのが困難な場合には、患者本人の承諾を得て、家族が代わりに受診できます。
③セカンドオピニオンを受ける医療施設を選ぶ
セカンドオピニオンを依頼する医療施設は、主治医に紹介してもらったり、がん相談支援センターに相談したりして探すことができます。患者本人がセカンドオピニオン先の医療施設へ出向くのが難しい場合は、パソコンやスマートフォンを使ったオンライン形式を提供している医療施設を検討しましょう。主治医と別の視点からのアドバイスを得るためには、罹患しているがんに対して専門性の高い医師や、放射線科の医師を選ぶことをおすすめします。
④受診当日までに資料などを準備する
セカンドオピニオンで適切なアドバイスを得るために、主治医に今までの治療経過と検査結果などの資料作成をお願いします。限られた相談時間を有効活用できるように、質問したいことを前もってメモにまとめておきましょう。質問内容がまとまらない場合は、がん相談支援センターにサポートを依頼すると良いです。
質問内容のまとめ方を詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
>>セカンドオピニオンを有効活用するために。がん治療における質問例や相談内容、聞くことのまとめ方を解説
入院中のセカンドオピニオンを家族が代わりに相談する方法

患者本人が入院している間に、家族が代わりにセカンドオピニオンを受診する方法や注意事項について解説します。
代理相談が認められるケース
セカンドオピニオンの代理相談は、患者本人の承諾があることが大前提です。
患者本人が入院中であるなど、医療施設に来院することが難しい場合は、家族が代わりに受けられます。そのほか、患者本人が高齢者や15歳未満の子どもで、判断能力が不十分であると主治医が判断した場合も、家族が代わりに受診することが認められます。ただし、紹介状に患者が合理的判断ができない状態であることが記載されている必要があるため注意しましょう。
家族が代理相談するにあたって必要な書類
通常のセカンドオピニオンと同様に、家族が代わりに受診する際も今までの治療経過や検査結果などの資料が必要です。家族が代わりに受ける場合は、患者本人の同意書や患者との関係を証明する書類も求められる場合があります。
家族が代わりにセカンドオピニオンを受診する注意点
セカンドオピニオンは、主治医から提示された病状や治療法に対して、患者や家族の気がかりな点を解消し、納得して治療を進めるための「相談」です。原則的には患者本人の意思が重要であって、家族の考えや意思を優先しないように注意しましょう。最終的な方針については、患者本人・家族・主治医と三者での話し合いで決定します。
入院中におけるオンラインセカンドオピニオンの活用方法

入院中の患者さんでも受診可能なオンライン形式のセカンドオピニオンについて解説します。
オンライン形式によるセカンドオピニオンとは
オンライン形式によるセカンドオピニオンは、パソコン・スマートフォン・タブレットなどの端末を使用し、インターネットを通じてビデオ通話形式でおこないます。
患者や家族が医療施設に来院することなく、入院中の病室など都合の良い場所で、主治医以外の中立的な立場の医師から直接アドバイスを聞くことができます。オンライン形式でも、主治医から事前に提供された治療経過や検査結果などに基づき、相談がおこなわれます。
入院中にオンラインセカンドオピニオンを利用するメリット・デメリット
入院中にオンライン形式のセカンドオピニオンを利用するメリットとデメリットは以下のとおりです。
【メリット】
- 医療施設へ出向く負担がないため、入院中の患者さんの負担軽減ができる
- 遠方の医療施設にいる専門医のアドバイスを求めたいときでも、直接出向く必要がない
- 患者と家族が離れた場所に住んでいる場合でも、それぞれの場所から参加することが可能
- 家族がセカンドオピニオンに参加する場合、移動にかかる時間や費用の負担を減らせる
【デメリット】
- 対面と異なり、お互いの表情や雰囲気が分かりにくいため、誤解が生じる可能性がある
- 病状によっては、オンライン相談が推奨されないケースもある
- 通信環境に左右されるため、途中で音声が途切れたり、画像が乱れたりすることで、相談が十分にできない可能性がある
- 電波状況によっては、ビデオ通話が繋がらず、電話に切り替えられる可能性もある
オンラインセカンドオピニオンを受診する際に必要な準備
通常と同じく、主治医から今までの治療経過や検査結果などを事前にセカンドオピニオン先へ送ります。
患者さん側で準備するものは、以下のとおりです。
- 聞きたいことをまとめたメモ
- Wi-Fiなど安定したインターネット回線
- パソコンやスマートフォンなどカメラとマイクが付いたデバイス
支払い方法についても事前に確かめておきましょう。オンライン形式でおこなう医療施設では、クレジットカード払いを求められることが多いです。
入院中におけるセカンドオピニオン受診後の選択肢

入院中にセカンドオピニオンを受けた後、どのような選択肢があるか解説します。また転院することになった際の注意事項についてもみていきましょう。
現在の入院先で治療を続ける
セカンドオピニオンを受けて、主治医の提案を承諾できるときは、現時点の入院先で治療を続けましょう。セカンドオピニオンの見識が主治医と同じだった場合でも、ほかの医師から追加の情報を得ることで、病状や治療への理解が深まり、より安心して治療に臨むことができます。主治医と異なる言葉で説明を受けることにより、さらに理解しやすく感じることもあるのです。
希望する治療を受けられる医療施設へ転院する
セカンドオピニオンの結果、患者の望む治療が、主治医から提案されたものと異なる場合や、現時点の病院ではおこなえない方法である場合は、転院を視野に入れることがあります。
転院を希望する場合は、現時点の主治医に申し出て、改めて今までの治療経過や検査結果などの資料を作成してもらいます。転院希望先の医療施設に資料を提出して、受け入れてもらえるかどうかを確かめましょう。転院先での受け入れが決まったら、転院に向けて手続きや日程調整をおこないます。
入院中の転院にともなうリスク
入院中の転院を念頭におく場合、いくつかのリスクを把握しておきましょう。
転院を希望しても、病床の空きなど転院先の状況や患者の病状によっては、受け入れを断られることがあります。 また、転院の手続きや新しい病院での診察・検査などに時間がかかり、病状が悪化したり治療開始が遅れたりする可能性があるのです。
患者の状態によっては介護タクシーなど、一般的な交通手段が使えず移動費用がかさむことも考慮しておきましょう。
入院中のセカンドオピニオンに関するよくある質問
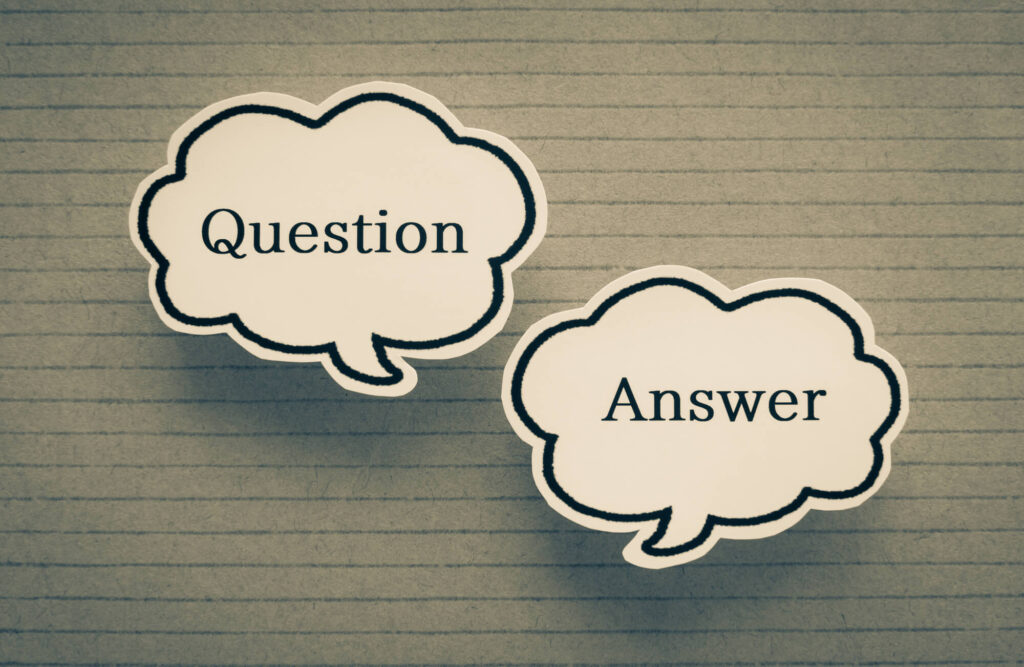
入院している際にセカンドオピニオンを利用するにあたって、よくある質問をQ&A方式で解説します。
重篤な状態でもセカンドオピニオンを受けられる?
がんの種類や進行状況によっては、治療の開始が遅れることで状況が悪化するリスクも考えられます。セカンドオピニオンを考慮する際は、治療法を決定するまでにどのくらいの時間制限があるか主治医に確かめておきましょう。
セカンドオピニオンを受けるために一時退院する必要はある?
セカンドオピニオンのための一時退院は、必須ではありません。患者本人が受診できなくても家族が代わりに相談することができます。近年では、オンラインによるセカンドオピニオンをおこなう医療施設も増えており、来院が難しい入院中の患者さんでも直接医師と話せる機会があるのです。
家族だけでセカンドオピニオンを受けても意味がある?
家族が代わりにほかの医師からのアドバイスを聞くことで、病状や治療への理解を深め、今後の治療法について患者本人や主治医とより前向きに話し合うことができます。多くの医療施設が、入院中などの理由で患者本人が来院できない場合に、家族によるセカンドオピニオン相談を認めています。
ただし、家族の思い込みで判断しないように、患者本人の意思を前もって確かめておくことが大切です。
まとめ

入院中でもセカンドオピニオンを受けることは可能です。患者本人が来院できない場合は、家族による代理相談や、近年ではオンライン形式も利用できます。
大切なことは、主治医から病状や治療法が提示された適切な時期に受けて、十分な情報収集をおこなうことです。
入院中に提示された病状や治療法で気がかりな点が生じたときは、まず主治医ときちんと話し合い内容を理解した上、状況に応じてセカンドオピニオンの意向を遠慮なく申し出ましょう。自分にとって納得のいく治療を選ぶために、積極的に制度を活用することをおすすめします。