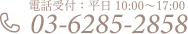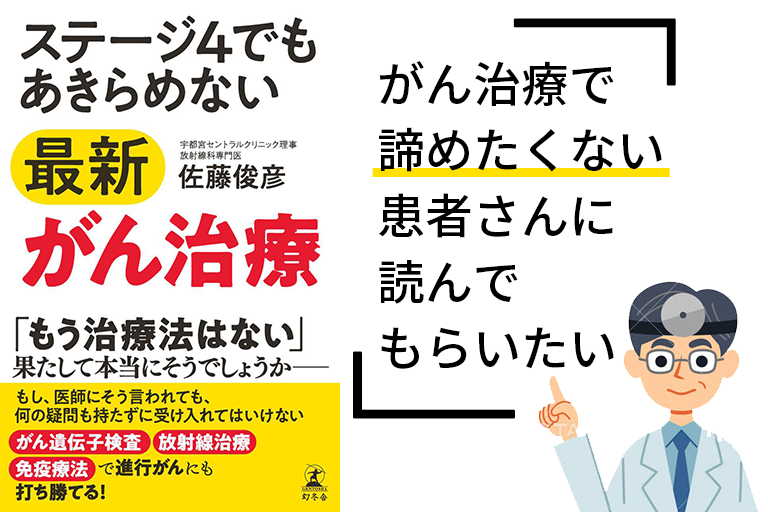3,571
3,571
セカンドオピニオンを受けた後に元の病院に戻ることはできる?選択肢について解説

近年では、セカンドオピニオンを受けることが当然の権利として受け入れられるようになってきました。このことは、多くの病院でセカンドオピニオン外来を開設していることからも明らかです。
しかし、受診後に主治医へ転院の希望を伝えるにはどうすればよいのか、セカンドオピニオンを受けた後に元の病院に戻ることはできるのかなど、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、セカンドオピニオンの詳細や受診後の選択肢について解説していきます。ご興味のある方は、ぜひ最後までご一読ください。
目次
セカンドオピニオンの定義

「セカンドオピニオン」を直訳すると「2番目(Second)の意見(opinion)」となり、医療の世界では、「主治医以外の医師に意見を求めること」を指します。特に、がんをはじめとした難治性疾患ではセカンドオピニオンを求める人が増加の傾向にあり、認知度も年々高くなっています。
セカンドオピニオンは、患者さんが納得できる最善の治療方法を選択することを目的として受診するものです。しかし、多くの人が誤解していると考えられるのが、「セカンドオピニオンは転院を目的とせず、元の病院に戻ることが原則」だということです。決して、主治医や病院を変えることを目的としたものではありません。
そのため、「主治医と合わない」「もっとよい治療方法があるはず」など、主観的な動機で転院をくり返すドクターショッピングとは大きく異なります。
受診する際は、あくまでも今後の治療方針を検討するために主治医以外の医師の意見を求めるものである、ということを十分に理解しておきましょう。
セカンドオピニオンを受けた後に元の病院に戻ることはできるのか
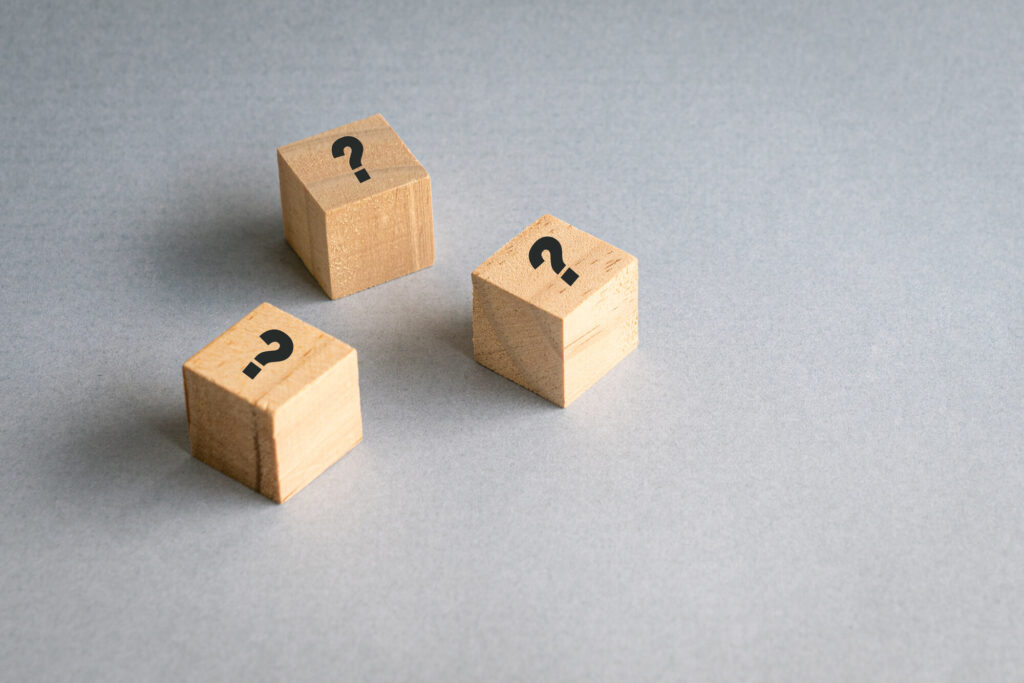
セカンドオピニオンを受けた後に元の病院に戻ることについては、何の問題もありません。
セカンドオピニオンは、患者さん自身が現在おこなっている治療以外の可能性を求めたり、不安や疑問を解消したりすることを支援する仕組みとして機能するものです。その機能を正しく理解して受診することで、より納得のいく決断をすることができるでしょう。
セカンドオピニオンのメリット・デメリット
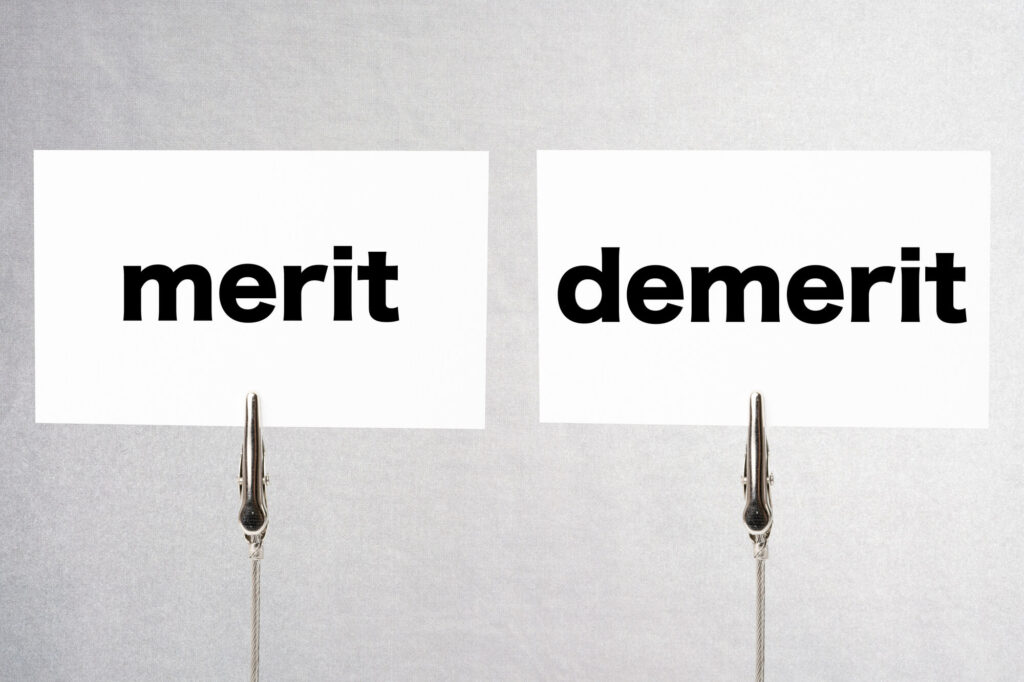
セカンドオピニオンのいちばんのメリットは、主治医と違う意見が示された場合、その後の選択肢の幅が増えるということです。
ただし、国の指定した「がん診療連携拠点病院」では、エビデンス(科学的根拠)に基づいた標準治療(外科的手術・化学療法・放射線療法)を最善の治療方法として採用することがほとんどです。そのため、がん診療拠点病院のあいだでは、意見に大きな違いがみられないことが多いと考えられます。
しかし、たとえ主治医と同じ意見であったとしても、ほかの医師から話を聞くことにより、病気や治療への理解が深まるというメリットが得られます。
一方、デメリットとしては、医療費やそのほかの金銭的な負担が大きくなることが挙げられます。自由診療の扱いとなるため全額が自己負担となり、紹介状や画像、各種検査データの入手にも費用がかかります。さらに、自宅から離れた病院を受診することを検討している場合は、交通費や宿泊費の負担も考慮する必要があります。
また、複数の病院を受診しているあいだに病気が進行するリスクがあります。事前に受診先の病院のリサーチを慎重におこなうなど、あまり時間をかけすぎないようにすることも重要です。
セカンドオピニオンの受診の流れ
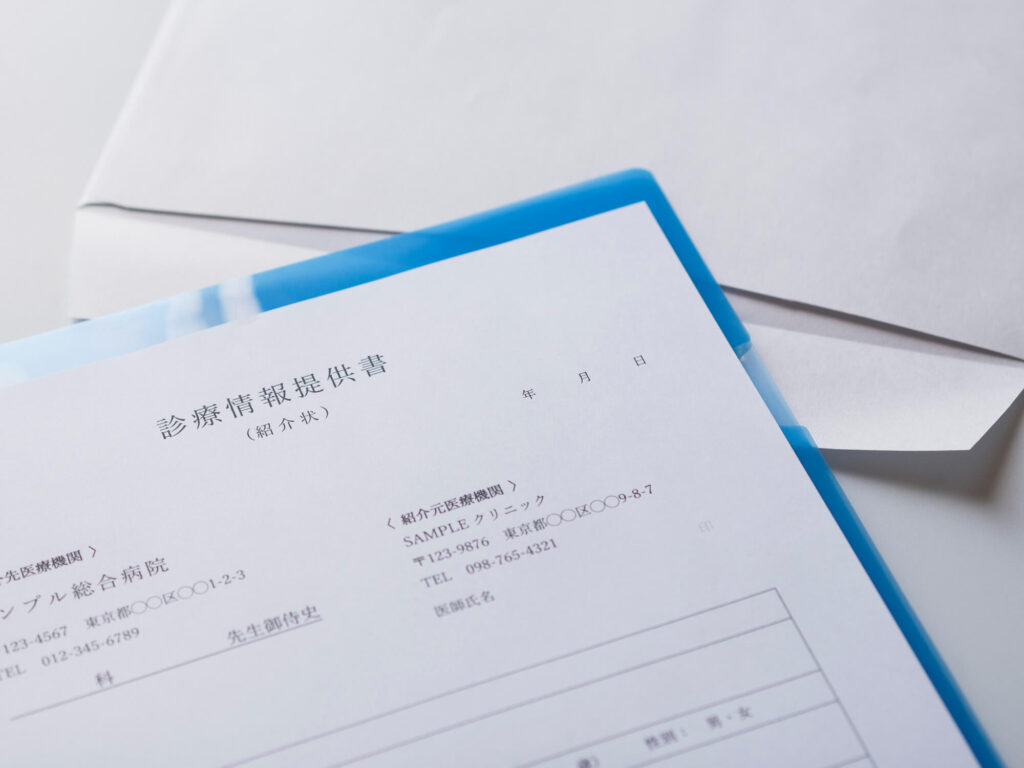
ここからは、受診の流れとポイントについて解説していきます。トラブルなくスムーズに受診できるよう、ぜひ参考にしてください。
現在の主治医の診断・意見を理解する
まず、現在の主治医の診断や意見・治療方針について、患者さん自身がしっかりと理解することが大切です。また、病状や進行度も把握したうえで、「なぜセカンドオピニオンを受けたいのか」という動機についてもあらためて整理しておく必要があります。
主治医の診断・意見への理解が不十分で動機もはっきりしないという状態で受診すると、ただのドクターショッピングで終わってしまう恐れがあります。受診の機会を最大限に生かすためにも、主治医の意見(ファーストオピニオン)を理解しておくようにしましょう。
セカンドオピニオンの受診先を決める
受診を決断したら、具体的に病院選びをはじめましょう。
セカンドオピニオンに特化した専門の外来を開設している病院もありますが、従来の診療科のなかで相談を受けている場合もあります。
インターネットで「○○(病名)セカンドオピニオン」などのキーワードで検索をすると、複数の病院が候補として挙がってきます。その候補のなかから、自身の希望や条件にあう病院を選ぶのもひとつの方法です。
また、がん診療連携支援拠点病院には「がん相談支援センター」が設置されており、その地域でセカンドオピニオンの受診が可能な病院や、対応している診療分野についての情報などを提供しています。がん相談支援センターは、実際にその病院を受診していない患者さんやご家族も無料で利用することができますので、受診先検討の際に相談してみてもよいでしょう。
全国のがん診療連携支援病院は、以下のサイトから検索することができます。
>>国立研究開発法人国立がん研究センター「がん情報サービス」
なお、15歳から39歳のAYA世代(Adolescent and Young Adult=思春期および若年成人)のがん患者さんに対して、その世代に特化した相談支援を提供している病院もあります。
現在、東京都では東京都立小児総合医療センターと聖路加国際病院に「AYA世代がん相談情報センター」を開設しています。
>>東京都保健医療局 東京都がんポータルサイト「AYA世代がん相談情報センター」
AYA世代に特有の問題である学業や仕事・育児と治療の両立、妊孕性の温存などをサポートする役割も担っており、今後は同様の相談支援窓口が増えていくと考えられます。
現在の主治医にセカンドオピニオンの希望を伝える
受診する病院が決まったら、現在の主治医に受診の意思を伝えます。
「主治医が気を悪くするのではないか」と感じる人も多いかと思いますが、現在ではほとんどの医師が肯定的にとらえてくれるため、心配する必要はありません。また、受診にあたっては、紹介状や画像データ・各種検査結果などを用意してもらいましょう。
はっきりと患者さん自身の気持ちや意思を伝えておくことで、受診後もスムーズに元の病院に戻ることができるでしょう。また、受診先の病院を選びきれずに悩んでいる場合は、主治医に相談して紹介してもらうことも検討してください。
現在の主治医とのコミュニケーションを良好にすることも、受診をうまく進めていくポイントのひとつです。しかし、どうしても言いづらいという場合は、看護師やソーシャルワーカーなどの医療スタッフに相談するのも方法のひとつです。
セカンドオピニオンの受診先の予約をとる
主治医に受診の意思を伝え、紹介状や各種データ入手のめどがついたら受診先の予約をとります。多くの病院では電話での受付をおこなっていますが、なかには、ホームページから申し込みを受け付けている病院もあります。
予約の際は、予約日時・相談時間・受診方法・当日持参するものを必ず確認してください。
また、最近よくみられるのが、主治医から入手したデータを持参して一般外来で相談をするというケースです。これは明らかなルール違反であり、一般外来を受診する患者さんの診察や治療を妨げるなど、患者さんだけではなく受診先の病院に大きな不利益をもたらす行為です。正しく受診の手続きを踏み、マナーを守ることを心がけましょう。
セカンドオピニオンを受診する
受診前には、あらかじめ「聞きたいこと・伝えたいこと」をメモにまとめておくとよいでしょう。なぜなら、初めての医師・病院で緊張のあまり、言いたいことが言えなくなることが考えられるからです。
大切な受診の機会で納得できる結果を得るためにも、事前に準備しておくことをおすすめします。それでも不安が残るという場合は、家族や信頼できる人に同席してもらうと安心でしょう。
セカンドオピニオンの受診後にするべきこと

ここからは、受診後に患者さんや場合によってはそのご家族がするべきことについて説明していきます。
現在の主治医に結果を報告する
「元の病院に戻ることが原則」と前述したとおり、受診後は主治医にその結果を報告することが必要です。
セカンドオピニオンの受診結果は、その日に直接受け取れる場合と、紹介元である主治医に郵送・メールなどで送られる場合があります。受診時に結果が入手できる日程を確認し、それにあわせて現在の主治医の予約をとって結果を報告するようにしましょう。
今後の治療方針を決める
現在の主治医とセカンドオピニオンの意見をすり合わせることにより、今後の治療方針を決めていきます。
主治医とセカンドオピニオンの意見が一致していれば、安心して現在の治療を継続していくことができるでしょう。しかし、違う意見であった場合、その意見に対しての主治医の見解も参考にしながら、今後どのような方針のもとで治療をおこなっていくのか、患者さん自身が決めることが求められます。
治療方針を自ら決めることは簡単なことではありません。患者さんにとって最善の治療方法を選ぶためにも、前項で説明したように主治医と十分にコミュニケーションをとっておくことが大切です。
セカンドオピニオンを受けた後の選択肢

受診後の選択肢として、以下の3つが挙げられます。
- 元の病院に戻る
- セカンドオピニオンの受診先に転院する
- さらに別の病院を探す
ここでは、以上の3つの選択肢について詳しくみていきます。
元の病院に戻る
基本的には元の病院に戻るのが原則となります。
特に、主治医とセカンドオピニオンの診断・意見が一致した場合は、元の病院に戻るのが最善の方法だといえるでしょう。また、セカンドオピニオンから示された治療方針を選んだ場合、元の病院で治療をおこなうことが可能であれば、現在の主治医のもとで治療を継続することができるでしょう。
セカンドオピニオンの受診先に転院する
セカンドオピニオンの治療方針を選び、その治療が元の病院に戻ると受けられないという場合は転院が選択肢のひとつとなります。たとえば、がんで標準治療以外の放射線療法や免疫療法などを希望する場合、治療を受けられる病院が限られるため、転院が必要になるケースがあります。
はじめに転院することが可能かを確認し、転院が決まったら主治医にこれまでの治療経過や検査結果を転院先に引き継いでもらいましょう。
また、転院先での治療後は、経過観察のために元の病院に戻ることも一般的です。
さらに別の病院を探す
セカンドオピニオンで納得できる意見が得られなかった場合、さらに別の病院に意見を求めることも方法のひとつでしょう。これを、サードオピニオンと呼びます。
サードオピニオンを受診する際も、セカンドオピニオンと同じステップを踏むことになります。そのため、そのあいだに病気が進行して手遅れになるというリスクがともないます。また、受診の費用や手間など、患者さんやご家族の負担が増えることも考えられるため、ドクターショッピングにならないように慎重に受診先を探すことが重要です。
セカンドオピニオンについてよくある質問

最後に、セカンドオピニオンについてよくある質問にお答えしていきます。
セカンドオピニオンは主治医に内緒で受けられる?
主治医に内緒で受けることは、原則的に不可能だといえるでしょう。なぜなら、受診時には紹介状や画像データ、そのほかの検査結果を持参しなければならないからです。これらのデータを主治医に内緒で用意するのは、非常に難しいと考えられます。
その後の治療のためにも、受診の意思は必ず主治医に伝えることをおすすめします。
セカンドオピニオンを希望したら怒る医者もいる?
現在では、セカンドオピニオンが患者さんにとって大切な権利であることが広く認知されています。
もし、希望を伝えたときに怒るような医師であれば、医師としての倫理観を疑わざるを得ません。そのような場合は、看護師やソーシャルワーカーなどの医療スタッフに相談するのもひとつの方法です。
セカンドオピニオンの料金はどれくらいかかる?
自由診療扱いとなるため、料金には大きな開きがあります。
東京都の病院では、相談時間が30分~1時間の場合、料金は1万円~5万円弱です。また、オンラインでの相談がおこなわれている場合は、対面よりも料金が低く設定されていることが多いようです。
詳しくは、対象の病院に確認するようにしましょう。
まとめ

本記事では、「セカンドオピニオン受診後に元の病院に戻ることができるのか?」をテーマに詳しく解説してきました。
セカンドオピニオンの受診後は、元の病院に戻ることが原則となります。
しかし、患者さんがセカンドオピニオンの意見を選択したものの、元の病院ではその治療をおこなっていない場合は転院が必要になります。そのようなケースでは、治療後の経過観察のために元の病院に戻ることも一般的です。
また、さらに別の病院に意見を求めてサードオピニオンを受ける方法もあります。ただし、病気の進行や患者さん・家族の負担を十分に考慮する必要があるでしょう。
セカンドオピニオンを有効に活用するための情報については、以下の記事でも詳しく解説していますので、よろしければぜひご覧ください。
>>セカンドオピニオンを有効活用するために。がん治療における質問例や相談内容、聞くことのまとめ方を解説