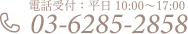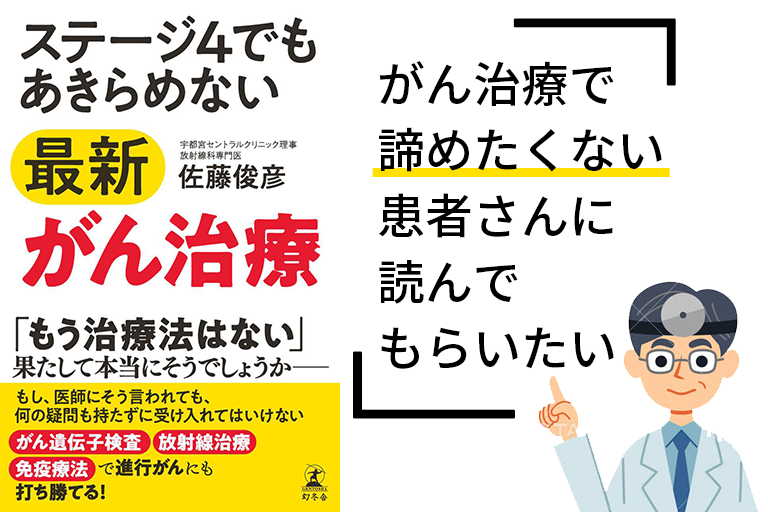2,310
2,310
胃がんの末期・ステージ4における治療の選択肢について

胃がんが末期・ステージ4まで進行したとき、患者さんやご家族は大きな不安を抱えることでしょう。
ステージ4の5年生存率は厳しい数値となりますが、薬物療法・放射線治療・手術・免疫細胞療法など、症状緩和や延命を目指す治療の選択肢がさまざまあります。大切なことは、自身のがんの特徴を把握し、自分にとって適切な治療法を選択することです。
今回は、胃がん末期における治療方法や検査方法、セカンドオピニオンの活用まで、治療を選択するのに必要な情報を詳しく解説します。
目次
胃がん末期とは?ステージ4の基本知識

胃がん末期(ステージ4)について、定義や転移しやすい場所などを解説しましょう。
胃がん末期・ステージ4の定義
胃がんのステージは、TNM分類によって決定します。それぞれの要素は以下のとおりです。
- T:がん組織の広がり具合
- N:胃の周囲にあるリンパ節に対する転移の有無
- M:胃から離れた臓器やリンパ節に対する転移の有無
末期といわれるステージ4は、がんの広がり具合にかかわらず遠隔転移が起きている状態、もしくは、遠隔転移がなくてもがん組織が胃の表面を突き抜けて隣接するほかの臓器まで広がっている状態を指します。
胃がん末期・ステージ4の転移の特徴
胃がんは、初めは内側の粘膜に発生しますが、進行するにつれて外側の漿膜(しょうまく)を超えて広がり、隣接する大腸や膵臓などに広がっていきます。漿膜を超えると、お腹のなかの臓器を覆う薄い膜にがん細胞が散らばったように広がることもあるのです。がん細胞がリンパ節に転移すると、血液の流れに乗って肝臓や肺に転移します。
胃がん末期・ステージ4の余命について

胃がん末期(ステージ4)における5年生存率や、予後に影響を与える要因について解説しましょう。
胃がん末期・ステージ4の5年生存率
胃がん全体の5年生存率は、70.2%です。がん組織が胃にとどまっていて、ほかの臓器やリンパ節に広がっていない「限局がん」では96.7%、がん組織が胃の近くのリンパ節や臓器まで広がっている「領域がん」では51.9%となります。
がんが進行するごとに5年生存率は低下し、遠隔転移のあるステージ4では6.3%と非常に厳しい数値となるのです。
参考:国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計結果閲覧システム 胃がん5年生存率」
胃がん末期の予後に影響する要因
胃がん末期の予後に影響する主な要因は、がんの組織型分類と転移場所です。
がんの組織型は、一般型と特殊型に分類されます。一般型は、さらに分化型と未分化型に分けられ、分化型は比較的進行が緩やかですが、未分化型は進行のスピードが速く予後不良になる可能性があるのです。
がんは腹膜に転移すると「腹膜播種」という、がん細胞が腹膜全体に散らばったような状態になります。腹膜播種は、抗がん剤が効きにくいとされ、早期からお腹の張り・吐き気などが現れます。症状が進行すると腹水が溜まりやすくなり、がん性腹膜炎を発症して、治療が困難になるのです。
胃がん末期に現れる主な症状

胃がん末期に現れる主な症状について確認していきましょう。
胃がん末期の代表的な症状
末期まで進行すると、がんに侵されたことで胃での消化が困難になるため、吐き気・食欲不振・体重減少が現れるようになります。さらに体の水分調節も難しくなり、腹水・お腹の張り・むくみが起こりやすくなるのです。
がん組織から出血するため吐血や下血があり、継続的に出血することで貧血を伴うことがあります。
転移に伴う症状
胃がんが離れた臓器に転移すると、転移した臓器によってさまざまな症状がみられます。
肝臓に転移した場合は、お腹や背中の激痛・倦怠感・黄疸が現れます。肺に転移すると、継続的な咳・血痰・息切れ・息苦しさが現れるのです。
胃がん末期・ステージ4における治療の選択肢

胃がん末期(ステージ4)で選択できる可能性のある治療方法について解説しましょう。
薬物療法
胃がんの薬物療法では、一次化学療法〜四次化学療法まで段階を追って治療します。
がんの病理分類や全身状態によって、細胞障害性抗がん剤・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬が使用されます。それぞれの薬剤の特徴などを確認しましょう。
細胞障害性抗がん剤
細胞障害性抗がん剤は、がん細胞が増殖する仕組みを阻害してがんを小さくする働きがあります。胃がんでよく使われるものは、ピリミジン代謝拮抗薬・白金製剤・タキサン系抗がん剤です。
一般的には、複数の抗がん剤を組み合わせて治療をおこないます。
分子標的薬
分子標的薬は、がん細胞にある特定の分子をターゲットにして作用する薬です。胃がんでは、HER2タンパク質を過剰に発現しているタイプがあります。HER2タンパク質は、胃がん細胞の表面にあり、がんの増殖にかかわっているのです。
病理組織を検査して、HER2陽性と診断された場合は、HER2タンパク質をターゲットにした分子標的薬を使って治療します。
免疫チェックポイント阻害薬
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫細胞からの攻撃から逃れるシステムに働きかける薬です。胃がんでは、一次化学療法をおこなっても効果がみられない場合や再燃した場合にMSI検査をおこない、MSI-Highと診断されると免疫チェックポイント阻害薬が使用されます。
MSIとは、マイクロサテライト不安定性を指します。MSI-Highの患者では、DNA複製時に起きるエラーを修復する機能が低下してしまい、エラーが取り除かれない状態でDNAが複製されるため、がんが発生しやすい状態になるのです。
放射線治療
胃がんの放射線治療は、ステージ4のように手術が難しいケースや痛み・出血の症状緩和でおこなわれます。胃の周りにある臓器に対して、放射線によるダメージを少なくするために、強度変調放射線治療(IMRT)やトモセラピーなど、がん組織に集中して放射線を照射できる装置で治療がおこなわれます。
緩和手術
胃がん末期(ステージ4)では、がん組織によって、出血したり消化管が詰まったりした場合に、症状をやわらげる目的で手術がおこなわれます。安全に手術がおこなえる場合は胃の切除をおこないますが、胃の切除が難しい・危険をともなう場合は、胃と空腸をつなぐバイパス手術がおこなわれるのです。
対症療法
がんの影響で起こる症状に対しては、以下のように軽減する治療がおこなわれます。
| がん性疼痛 | オピオイド系鎮痛剤の投与・神経ブロック |
| 腹水 | 利尿剤の投与・腹水穿刺・シャント手術 |
| 食欲不振 | 経腸栄養剤の投与 |
| 吐き気 | 制吐剤の投与 |
免疫細胞療法
免疫細胞療法は、患者本人の血液から免疫細胞を採取し、人工的に増やしたり活性化させたりしてから、再び体内に戻す方法です。自分の免疫細胞を利用するため、副作用が少ないとされています。
薬物療法や放射線治療と併用可能です。免疫細胞療法には、BAK療法、樹状細胞療法、NK細胞療法などがあります。
胃がん末期・ステージ4で適切な治療を選択するための診断方法

胃がん末期・ステージ4において、適切な治療を選択するために必要な検査について解説しましょう。
CT検査・MRI検査
CT検査やMRI検査では、ほかの臓器やリンパ節への転移、胃と隣接する臓器への広がり具合を調べます。CT検査はX線、MRI検査では磁気を使用して、体の断面像を撮影します。CT検査では、より詳しい検査画像が得られるように、造影剤を使用することがあるのです。
PET-CT検査
PET-CT検査は、放射性フッ素を付けたブドウ糖に似た性質を持つ薬剤を使用して、全身にわたるがんの転移や再発の有無を調べる検査です。がん細胞が、健康な細胞よりもブドウ糖を多く取り込む性質を利用しています。PET-CT検査では、がん組織の活性度と位置を同時に調べることが可能です。
遺伝子検査
がんは遺伝子の変化によって発症します。がん遺伝子パネル検査は、手術や検査で採取したがん組織や血液を使用して、一度の検査で多数の遺伝子について調べることが可能です。どの遺伝子について変化が起きているか判明すると、がんの特徴にもとづいた治療を選択できます。
ただし、ステージ4まで進行すると、最初に胃に発生したがん組織と転移先のがん組織で遺伝子変異が異なることが多くみられます。生検で十分な量のDNAが採取できないこともあるため、血液のみで検査できる方法が有効です。
胃がん末期・ステージ4でのセカンドオピニオン活用法

胃がん末期・ステージ4では、納得のいく治療を受けるために、ステージ判定や治療方針などについて、主治医とは異なる第三者の医師によるセカンドオピニオンを検討しましょう。セカンドオピニオンを受けるタイミングや注意点について解説しましょう。
セカンドオピニオンを受けるべきタイミング
セカンドオピニオンを受けるタイミングについて、3つのポイントに分けて確認しましょう。
診断内容に疑問や不安があるとき
胃がん末期(ステージ4)におけるステージ判定は、治療方針に大きな影響を与えます。
PET-CT検査やMRI検査などの画像診断については、誰が読影をするかが重要です。検査画像をより正確に読み取るには、経験が必要となります。画像診断の結果について、放射線診断専門医のような画像診断のスペシャリストから意見を聞くことも検討すると良いでしょう。
主治医から伝えられた診断結果と同じであっても、ほかの医師から別の視点で説明を受けることで、疑問や不安が解消されるケースが多くあります。
いくつかの治療方法を提案されて悩んだとき
胃がん末期では、がんの病状のみならず、全身状態なども治療方針にかかわります。そのため、複数の治療方法が提案されることがあるのです。どの治療が自分にとって適したものか悩んだときに、セカンドオピニオンを検討すると良いです。
第三者の医師から、主治医と異なる目線で説明を受けることで、提案された治療方法に対する理解が深まり、治療方針の決定の後押しになるでしょう。
主治医から提案されたもの以外の治療法があるか知りたいとき
胃がん末期(ステージ4)のように、ほかの臓器に転移していると、治療方法が限られてしまうケースもあります。主治医から提案された方法以外の治療があるか知りたいときも、セカンドオピニオンを活用すると良いです。
検査データや治療経過を、主治医と異なる目線で評価して次の治療方法を考えるため、新たな方法が見つかる可能性があります。結果として、主治医と同じ治療方針だったとしても、別の医師から補足的な説明を受けることで、納得して治療に臨むことができるのです。
セカンドオピニオンを検討するときの注意点
セカンドオピニオンを実際に受けたいと思ったときに注意する点を2つ解説しましょう。
主治医に内緒で受診しない
主治医との関係性が悪くなることを気にして、内緒でセカンドオピニオンを受けるケースがあります。主治医に内緒で受けると、それまでに受けた詳しい検査データや治療記録がない状態でセカンドオピニオンに臨むことになります。断片的な情報のみでセカンドオピニオンを受けても、適切な意見をもらうことが難しくなるのです。
胃がん末期・ステージ4では病状が進行しているため、できるだけ早く治療方針を決める必要があります。そのためにも、主治医にセカンドオピニオンの希望を伝えて、すみやかに受診できるような体制を整えることが大切です。
慎重にセカンドオピニオン医師を選ぶ
セカンドオピニオンを受けるときは、どの医師に依頼するかも重要です。胃がん末期まで進行すると、がんの広がり具合や転移の状況は一人ひとり異なります。胃がんについてより専門性の高い医師や、どの診療科に対しても中立的な立場である放射線科の医師など、主治医と違う角度で患者さんの病状を評価できる医師にお願いすると良いでしょう。
主治医にセカンドオピニオン医師の紹介をお願いすると、同じ診療科で似たような視点を持つ医師を紹介されるケースが多くみられます。できるだけ自分で探すことが望ましいですが、難しい場合はがん相談支援センターを利用すると良いです。
セカンドオピニオンの受診を検討している方は、以下の記事もあわせてお読みください。
>>セカンドオピニオンとは?費用や注意点など徹底解説
>>セカンドオピニオンのやり方とは?準備するものや手順など解説
まとめ

胃がん末期・ステージ4と診断されても、薬物療法・放射線治療・免疫細胞療法など、症状緩和や延命を目指すさまざまな治療の選択肢があります。大切なことは、PET-CT検査や遺伝子検査などで全身状態やがんの性質を把握し、その情報をもとに自分にとって適切な治療方法を選択することです。
診断や治療方針に疑問や不安があるときは、セカンドオピニオンを積極的に活用しましょう。胃がん専門医や放射線科医など、主治医と異なる視点を持つ医師からの意見は、治療方針の決定に役立ちます。まずは主治医と十分話し合い、必要に応じてセカンドオピニオンを検討し、納得のいく治療を受けるようにしましょう。