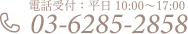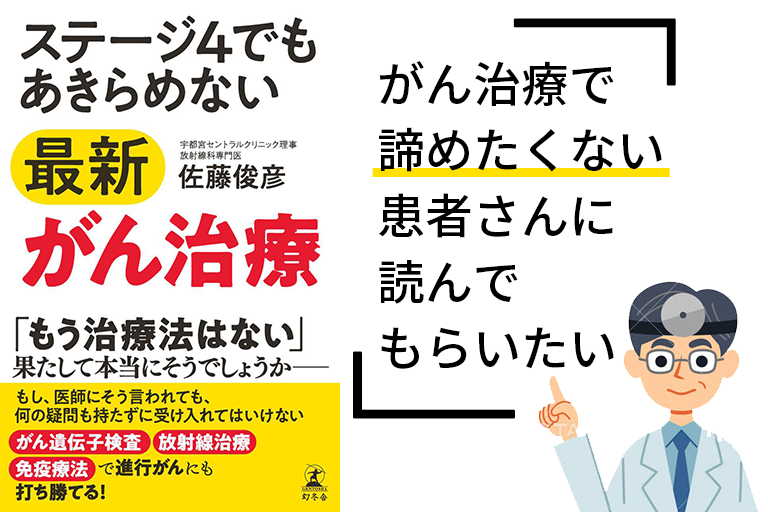421
421
がんの5大治療法とそれぞれのメリット・デメリットについて解説

がんと診断されたとき「どのような治療方法があるか」「自分に合った治療は何か」など悩む方がほとんどでしょう。がんの主な治療方法は5つあり、それぞれの治療方法について効果や副作用などをきちんと理解することが、納得のいく治療の選択につながります。
この記事では、がんの5大治療法についてメリット・デメリットを解説し、適切な治療方法を選ぶ際のポイントも紹介します。
目次
がんの5大治療法とは?

がんの5大治療法は、手術・放射線治療・薬物療法・免疫療法・先進医療の5つです。それぞれの概要や特徴をみていきましょう。標準治療と自由診療の違いについても解説します。
がんの5大治療法の概要と特徴
がんの5大治療法について、概要と特徴は下表のとおりです。
| 手術 | ●がんの病巣を切除する方法で、治療目的は根治と症状緩和の2つがある ●状況に応じて、周辺組織やリンパ節も一緒に切除することが一般的 ●近年では身体への負担を少なくする手術(腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術など)が普及 |
| 放射線治療 | ●高エネルギーの放射線をがん細胞に照射して消滅させ、増殖を抑える方法 ●手術が困難な部位のがんも治療できて、臓器を温存できる ●治療目的は根治と症状緩和の2つがあり、通院治療が可能 |
| 薬物療法 | ●抗がん剤、ホルモン剤、分子標的薬などの薬剤を用いてがんの増殖を防ぐ ●全身に広がったがん細胞を攻撃できる ●一部を除いて、通院治療で対応できる |
| 免疫療法 | ●体に備わっている免疫の力を強めることで、がん細胞を排除する ●免疫チェックポイント阻害薬が代表的で、転移や再発したがんにも適用される |
| 先進医療 | ●厚生労働大臣が承認した高度な医療技術を用いた治療で、有効性や安全性の評価段階にある ●がん治療に適用されるものには、陽子線治療、重粒子線治療などが挙げられる |
標準治療と自由診療の違い
がんの5大治療法は、さらに標準治療と自由診療に分類されます。それぞれの特徴を確認しましょう。
【標準治療】
- 科学的根拠に基づき、現在利用できるもっとも治療効果の高い方法であることが示されている
- 数多くの臨床データから有効性と安全性が評価されており、保険適用されている
【自由診療】
- 治療効果や安全性が科学的に十分に証明されていない方法が含まれることがある
- 治療費は、通常の診療や検査も含めて全額自己負担となる
がんの治療法を選ぶうえで必要なこと
がんの治療法を選ぶときにかならずやるべきことが3つあります。
1つ目は、自分の病状を把握することです。がんの種類・ステージ・全身の健康状態・既往歴などによって選択できる治療方法が異なります。
2つ目は、治療のメリット・デメリットを理解することです。提案された治療法について、それぞれの効果・副作用など、主治医から十分な説明を受けるようにします。
3つ目は、主治医と十分なコミュニケーションをとることです。治療方針について疑問や不安があれば、理解できるまで主治医に質問し、積極的にコミュニケーションをとるようにしましょう。
がん治療における手術のメリット・デメリット

がん治療における手術のメリットやデメリットを解説します。手術の主な種類や特徴なども確認しましょう。
手術の主なメリット
手術をおこなうメリットは、 がんの病巣を物理的に切除し、根治を目指せることです。主に、がんの発生場所が局所的で、周囲の組織やリンパ節に広がっていない早期のがんに適用されます。切除したがん組織を病理検査することで、がんの正確な診断と治療後の再発リスク評価ができます。
近年普及している腹腔鏡(胸腔鏡)下手術やロボット支援下手術は、従来の開腹(開胸)手術に比べて身体への負担が少なく、術後の回復が比較的早いです。
手術のデメリットと合併症
手術のデメリットとして、麻酔による副作用や手術による傷によって、全身の回復に時間がかかる場合があります。手術による感染症・出血・穿孔・深部静脈血栓症などの合併症が起こるリスクも考えられます。
手術でがんのある臓器を一部またはすべて切除する場合、臓器の機能が失われることで、術後の生活に大きな影響が出ることがあるのです。
手術によってがんがすべて取り除かれたように見えても、微小ながんが残り再発する可能性があることも頭に入れておきましょう。
手術の種類と適応となるケース
手術は、開腹(開胸)手術・腹腔鏡(胸腔鏡)下手術・ロボット支援下手術・内視鏡治療に分けられます。
| 開腹(開胸)手術 | ●体にメスを入れて、医師が患部を見ながら、がん組織を切除する従来からの方法 ●広範囲の切除が可能だが、回復に時間がかかる傾向 ●一般的には、がん組織が局所にとどまっている早期のがんで選択されることが多い |
| 腹腔鏡(胸腔鏡)下手術 | ●体の表面に小さな穴を開けて内視鏡や手術器具を挿入し、モニターを見ながらおこなう手術 ●体への負担が小さいため、近年普及している ●がんの種類や進行度によっては適応にならない |
| ロボット支援下手術 | ●腹腔鏡下手術をロボットで支援する方法 ●ロボット支援下手術では、関節が付いて手術器具の可動域が増えたため、これまで届きにくかった部分も切除できるようになった ●人間の手で起こる「手ぶれ」がなく、より正確に操作できる |
| 内視鏡治療 | ●口、肛門、尿道などから内視鏡を挿入し、カメラで確認しながら治療器具を用いて病変を切除する方法 ●早期のがんに対して適応される ●一般的に内視鏡治療で切除できるのは、食道がん・胃がん・十二指腸がん・大腸がん・膀胱がん |
がん治療における放射線治療のメリット・デメリット
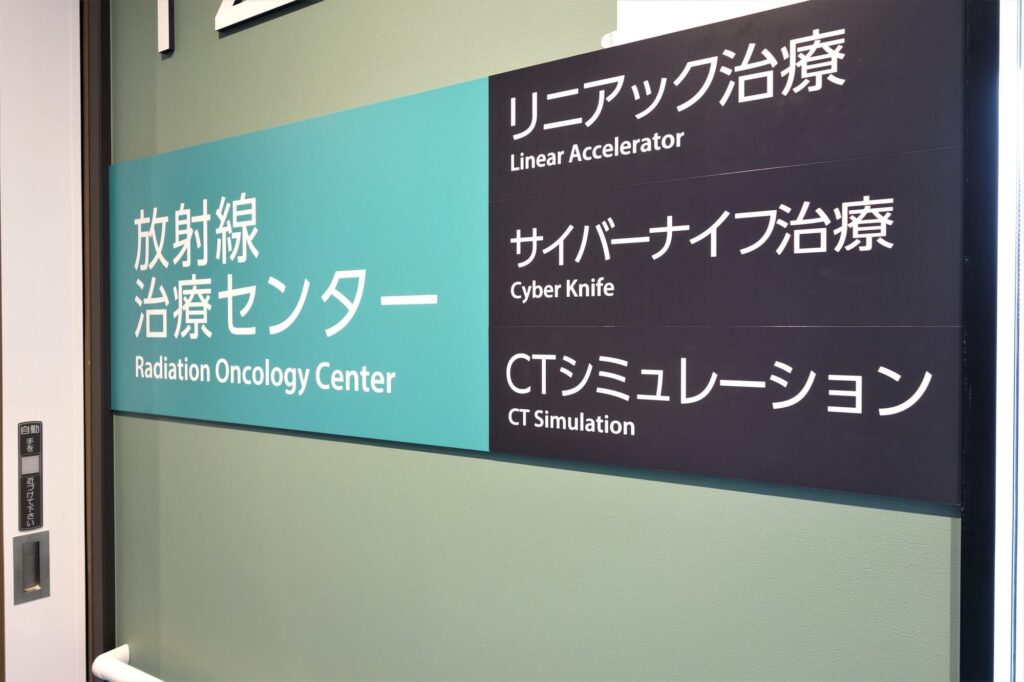
放射線治療のメリットやデメリットを確認しましょう。放射線治療の種類や特徴についても解説します。
放射線治療の主なメリット
放射線治療は、手術と異なり体の一部を切除しないため、臓器や機能を温存できます。手術で切除すると、後々大きな影響が出る臓器や組織のがんなど、手術が困難な部位にも適用可能です。治療時間は1回あたり10~30分程度となっており、通院治療で対応できます。
放射線治療のデメリットとリスク
放射線治療は、がん細胞だけでなく周囲の正常な細胞にも影響を与えるため、照射部位に皮膚炎や粘膜炎などの副作用が起こる可能性があります。治療終了から半年~数年後に、二次がんや不妊などの晩期の副作用がごくまれに発生することもあります。
副作用などのリスクを考慮し、1回あたりの放射線量を少なくして複数回に分けて照射するため、治療終了までに数週間かかることが一般的です。
がんが再発した場合、一度放射線治療をおこなった部位への再照射は制約があるケースもあります。
放射線治療の種類と特徴
放射線治療は、大きく外部照射と内部照射に分けられます。
外部照射には、X線・ガンマ線・電子線が用いられ、体の外から放射線を当てる一般的な方法です。照射する方法は、がんの形状に合わせて照射する強度変調放射線治療(IMRT)や、がん組織に高い線量を集中して照射する定位放射線治療(SRT/SBRT)などがあります。陽子線や重粒子線など、X線に比べてがん組織のみに高い線量を照射できる治療もあります。
内部照射は、放射線を発する物質を体内に入れて、直接がん組織に照射する方法です。放射性物質をがん組織の近くに挿入する密封小線源治療や、飲み薬または注射で体内に投与する非密封の放射線同位元素を用いた治療があります。内部照射は、主に舌がん、前立腺がん、子宮頸がん、甲状腺がんで適用されます。
放射線治療については以下の記事でもくわしく解説しています。
>>がん放射線治療について種類やメリット・デメリット、期間や回数、費用などを解説
がん治療における薬物療法のメリット・デメリット

薬物療法におけるメリット・デメリットをみていきましょう。薬物治療で用いる薬剤の種類や特徴についても解説します。
薬物療法のメリット
薬物療法では、手術や放射線治療では対応しきれない、体の広範囲に広がったがんや転移のあるがんも治療が可能です。薬物療法は単独でおこなわれることもあれば、がんの種類・ステージ・患者さんの全身状態に応じて、手術や放射線治療と組み合わせておこなうこともあります。
従来の抗がん剤に加えて、近年は分子標的薬など新しいタイプの薬剤が登場し、がんの遺伝子変異や特性に合わせて治療できます。
薬物療法のデメリットと主な副作用
塊を作るタイプのがんに対しては、薬物療法単独で根治を目指すことは難しいケースが多いです。細胞障害性抗がん剤では、がん細胞だけでなく健康な細胞にも影響を与えるため、脱毛・吐き気・倦怠感・血液障害などの全身的な副作用が生じやすくなります。分子標的薬の主な副作用は、高血圧・粘膜からの出血・皮膚症状・間質性肺炎などがあります。ホルモン剤の副作用では、ほてり・発汗・骨密度の低下などが起こりやすいです。
薬物療法の種類と特徴
薬物療法の種類と特徴は以下のとおりです。
| 細胞障害性抗がん剤 | ●がん細胞が増殖する仕組みの一部を阻害することで、がんを消滅させる ●正常細胞にも働きかけるため、脱毛や血液障害などの副作用が起こりやすい |
| 分子標的薬 | ●がん細胞に存在する特有のタンパク質を標的とし、その働きを抑えることで増殖を防ぐ ●がん細胞に特異的に作用するため、周囲の正常細胞への影響を比較的抑えられる |
| ホルモン療法 | 前立腺がんや乳がんのように、ホルモンに依存して増殖するがんに対して、ホルモン分泌を抑えたり、ホルモンの働きを抑えたりする |
がん治療における免疫療法のメリット・デメリット

免疫療法のメリット・デメリットを確認しましょう。免疫療法には、保険適用されるものと自由診療でおこなわれるものがあるため、注意点についても解説します。
免疫療法のメリット
免疫療法では、患者さん自身が持つ免疫細胞の力を利用するため、従来の抗がん剤治療で起こる吐き気や脱毛の副作用が起こりにくくなります。薬物療法と同じく、全身に作用する治療方法です。免疫療法は、がんの種類やステージによって、ほかの治療方法と併用することができます。
免疫療法のデメリットと注意点
免疫療法において、科学的根拠に基づいて効果が証明され、保険診療で受けられる治療は、一部のがんに対してのみ適応されています。自由診療でおこなわれている免疫療法の中には、効果や安全性が科学的に十分に証明されていない治療も多くあります。
免疫療法の種類や費用
免疫療法の主な種類と費用は以下のとおりです。
| 免疫チェックポイント阻害薬 | ●免疫療法のなかでも、免疫チェックポイント阻害薬は保険適用されている ●がん細胞が免疫細胞にかけているブレーキを解除し、免疫本来の力を回復させる薬 ●承認されているものは、PD-1阻害薬・CTLA-4阻害薬・PD-L1阻害薬の3種類がある ●支払う治療費は、保険負担割合により1割~3割で、高額療養費制度の対象となる |
| エフェクターT細胞療法 | ●エフェクターT細胞療法で、保険適用されているのはCAR-T細胞療法のみ ●がん細胞を攻撃する力を高める方法 ●患者の体内からT細胞を取り出し、がん表面にある特定の目印を認識する遺伝子を組み込んで増殖させてから、再び体内に戻す ●支払う治療費は、保険負担割合により1割~3割で、高額療養費制度の対象となる |
| 免疫細胞療法 | ●患者さん自身の免疫細胞(リンパ球など)を体外で増やしたり活性化してから体内に戻す方法 ●樹状細胞ワクチン療法、BAK療法、NK細胞療法などがあるが、すべて自由診療 ●自由診療による免疫細胞療法では、1クール(6回)の治療で180万円~400万円かかる |
免疫療法については以下の記事でもくわしく解説しています。
>>免疫チェックポイント阻害薬とは?わかりやすく解説
>>NK療法(細胞免疫療法)とは?効果や費用、治療の流れなどを解説
>>免疫細胞BAK療法の効果や費用、治療の流れなどを解説
がん治療における先進医療のメリット・デメリット

がん治療における先進医療のメリット・デメリットを確認しましょう。先進医療の種類についても解説します。
先進医療のメリット
先進医療では、従来のがん治療では治療が難しいケースについて、新しい治療の選択肢が広がる可能性があります。例えば、陽子線や重粒子線治療のように、従来の放射線治療よりも健康な組織へのダメージが少なく、がん組織に集中して放射線を照射できることがあります。先進医療の技術料自体は全額自己負担となりますが、入院費や検査費など通常の診療については保険診療の対象となり、経済的な負担が軽くなります。
先進医療のデメリット
先進医療の種類によっては、技術料が高額になります。先進医療は、適応される条件が定められているため、希望していても受けられない可能性があります。また、有効性や安全性が評価中であるため、必ずしも治療効果が得られるとは限らない点も注意しましょう。
先進医療は、厚生労働大臣への届出または承認を受けた特定の医療機関のみで実施されるため、場合によっては遠方の医療機関まで通院する必要があります。
がん治療における先進医療の主な種類と費用
先進医療Aとして届出されている方法は以下の2種類です。
| 陽子線治療 | ●放射線の1種である陽子線をがん組織に照射する ●先進医療の対象となるがんは、頭頚部腫瘍、脳腫瘍、肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍、転移性腫瘍において、根治が目指せるもの ●医療機関によって費用は異なるが、相場は288万円~294万円 |
| 重粒子線治療 | ●放射線の1種である重粒子線をがん組織に照射する ●先進医療の対象となるがんは、肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、転移性腫瘍で根治が目指せるもの ●医療機関によって異なるが、相場は314万円~350万円 |
がん治療法のメリット・デメリットを踏まえて適切に選択するには?

それぞれの治療法のメリットとデメリットを踏まえて、自分に合ったものを選ぶ際のポイントについて解説します。
治療効果と生活の質(QOL)を考慮する
治療法はがんの種類・ステージ・患者さんの全身状態などを総合的に判断して、主治医から提案されます。提案された治療法において、期待できる効果と限界を理解することが大切です。
それぞれの治療法における副作用や合併症など、治療中・治療後の生活への影響について十分に考慮し、主治医と相談しましょう。治療目標や自分の価値観をはっきりさせて、自分の納得のいく治療法を選ぶようにします。
治療にかかる費用・時間を検討する
保険適用される治療においても入院費・検査費・通院代など全体でどのくらいの費用がかかるか把握しましょう。通院治療をおこなう場合、1回あたりの治療時間や通院の頻度など、日常生活への負担も考慮します。
先進医療の技術料は、民間の医療保険が使用できる可能性があるため、事前に確認すると良いです。先進医療の技術料は高額療養費制度の対象外ですが、所得税の医療費控除の対象になります。
自由診療における治療費は、診察代から検査費用まですべて全額自己負担となります。自由診療のなかには、高額になるものもあるため、有効性や安全性について医師から十分な説明を受けましょう。
セカンドオピニオンを活用する
主治医から提案された治療法に対して、気がかりな点がある場合やほかの治療の選択肢について知りたい場合に、セカンドオピニオン制度を利用して、主治医以外の別の医師から意見を聞くことができます。セカンドオピニオンを受けることで、治療に関する理解を深めたり、新たな治療法が見つかったりして、より納得のいく治療選択につながります。
セカンドオピニオンでは、自分のがんに対してより専門的な知識を持っている医師や、どの診療科に対しても中立的な立場で意見を述べられる放射線科の医師に依頼すると、主治医と異なる視点から意見を聞けることが多いです。
まとめ

がんの5大治療法である手術・放射線治療・薬物療法・免疫療法・先進医療は、それぞれにメリット・デメリットがあります。がんの種類・ステージ・全身状態を考慮して治療方法が提案されますが、それぞれの治療方法における治療目的・期待できる効果・副作用を十分理解することが大切です。
ほかにも日常生活への影響や費用についても、主治医と積極的にコミュニケーションを交わして確認することが欠かせません。必要に応じてセカンドオピニオンを活用し、自分にとって納得のいく治療を選ぶようにしましょう。